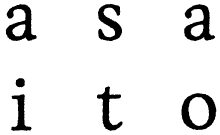私の手の倫理(20)届ける為のほぐす手
食事や絵画に音声など、時に塊では
受け手に届きにくいものがあります。
例えば噛んで飲み込むのが難しい
乳幼児や高齢の方には細かく柔らかく
した食べ物が好ましく、情景の陰影を
豊かな色にするには面に一色で描く
より朦朧感や点描というやり方が。
今回はそれらの概念の手が言語にも
当てはまった体験です。
私は食道がんで喉頭を摘出して現在
肉声の無い生活をしています。
言葉を文字に起こす以外には
人工喉頭=EL(エレクトロ ラリンクス)
を代替音声にしています。
ELは喉元に当てて声帯代わりの振動で
声を発しますが、「あ行」と「は行」の
区別がつきにくいです。
は=HaだとHで息が抜けてしまい
母音の「あ」だけが音として残りがちで
「はひふへほ」の発音のつもりでも
「あいうえお」に聞こえてしまいます。
そんな中、一音をほぐして
ふぁ、ふぃ、ふぅ、ふぇ、ふぉ、の
意識で出すと「は行」に聞こえ易くなる
のを発声教室で知りました。
今までは「星(ほし)を見る」が
「推し(おし)を見る」に聞こえがち
だったのも「ほ」→Fo(ふぉ)と発音して
かなり「は行」に寄せられました。
他にも「を」=(ぅお)や「わ」=(ぅあ)の
発音認識だと「あ行」の音との区別が
し易いです。
緩やかな色調の絵を近くでよく見たら
一見意外な色が混ざっていた、的な
手法。その事象に繋がる"音をほぐし
理想に近付ける"発話法でした。
様々な分野でも特性から存在の輪郭や
内側をほぐし和らげれば、新たな
可能性を見出だせるかもしれない
ですね。
(Y.I.さん)