私の手の倫理(19)声と言葉を探る手
2020年に食道がんで喉頭摘出以来
肉声の無い生活をしています。
会話は主に筆談やタブレットへの
文字入力と表情や身振りなどです。
あとは食道発声(食道入口部の粘膜を
声帯代わりに息で震わせて"げっぷ"の
要領で声を出す)です。こちらは未だ
日常会話レベルには厳しく、最近
咄嗟の時の発話に備えて人工発声器
EL(エレクトロ・ラリンクス)を使い
始めました。
ELは外してしまった声帯代わりの
振動を発する機械で、喉元で「あ」の
音がはっきり響く場所を探し当てて
口と舌を動かすと息を吐かなくても
声になります。
今までは指先を通して文字変換する
のに相手を待たせない為にもなるべく
凝縮した言葉を考え降ろしていたのが
瞬時に声を出せる様になり、喉で震える
拡声器がやって来たみたいです。
発音が鮮明な喉の位置は日によって微妙
に変わるのでELで声を出しながら触れ
決め、調節ボタンでイントネーションも
付けます。喋りのイメージはAI登場以前
のロボットといった所でしょうか。
これも自身の声、と認識されてゆくの
かな…と不思議な感じでもあり慣れる
のに日々手探りですね。
ちょっと悩ましいのがELは
は行=はひふへほ、で語感の輪郭が
何だかぼやけてしまい
あ行=あいうえお、になります。
例えば「星(ほし)を見る」は
「推し(おし)を見る」に聞こえるそう。
区別が出来る迄は「空のお星さま」など
伝わり易い発音と言葉を探すのも
課題になりました。
声と言葉を届ける方法が増えてきて
話す事の意識の使い方や感覚は
今後も色々面白くなりそうですね。
(Y.I.さん)
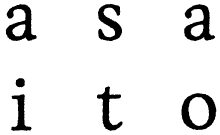





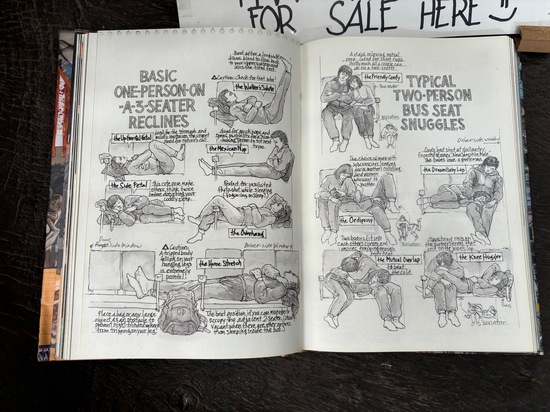 午後は、同じくタヒミックが手がけたカフェ
午後は、同じくタヒミックが手がけたカフェ
 ここの2階?スペースが映画館になっていて、ここでデラサル大学のEさんからレクチャーを受ける。テーマはKapwa。Kapwaはフィリピンサイコロジーの概念で、Other is a part of me/ shared identityのような意味らしい。フィリピンの学問は植民地の歴史を踏まえつつ自分たちの伝統を立ち上げようとする意識が高いように感じる。
ここの2階?スペースが映画館になっていて、ここでデラサル大学のEさんからレクチャーを受ける。テーマはKapwa。Kapwaはフィリピンサイコロジーの概念で、Other is a part of me/ shared identityのような意味らしい。フィリピンの学問は植民地の歴史を踏まえつつ自分たちの伝統を立ち上げようとする意識が高いように感じる。