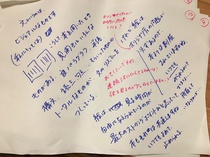異なる体の対談シリーズ、第一弾は西島玲那さんと加藤秀幸さんです。玲那さんは中途の全盲、加藤さんは先天性の全盲。必要な情報を的確に拾っていく断捨離モードの加藤さんと、見えるように見たいVR作り込みモードの玲那さん。見ることにこだわる自分の体に葛藤を抱える玲那さんに、加藤さんが深いエールを投げかけます。私が聞き手だったら絶対に出てこない言葉がたくさん飛び交いました。この対談に関する玲那さんとの往復書簡はこちら→③、④
加藤秀幸さんプロフィール
1975年東京都生まれ、在住。先天性全盲。システムエンジニア、ミュージシャン(E-bass guitar)。バンド「celcle」に所属。作曲を手がけることもある。映画『INNERVISION インナーヴィジョン』(2013)『ナイトクルージング』(2019)出演。インターナショナルスクール特別非常勤講師。好きなことは、料理、ものづくり、頭が痛くなるほど細かい作業(プラモ作成など)。
西島玲那さんプロフィール
1985年生まれ。15歳で網膜色素変成症を発症。19歳で失明。『記憶する体』出版後に伊藤と往復書簡を開始、視覚障害の方以外にもさまざまな体を持った方へのインタビューを開始。今回がその1回目。
◎VRが発動するタイミング
田中みゆき(加藤さんが出演した映画『ナイトクルージング』のプロデューサー) 何か書くもの借りてもいいですか。
加藤 シャーペンならもってますよ。
伊藤 加藤さんも書くんですね。
加藤 学校で講師やってるんで、印とかつけなきゃいけないから。
西島 印?
伊藤 学校の講師ってなんですか?
加藤 インター(ナショナルスクール)で、一般の学生に点字を教えるという講師をやってて。ドリルとかプラクティスとかあるので、あってるところとか間違っているところとか印をつけてます。
伊藤 英語の点字を教えてるっていうこと?
加藤 英語と日本語と両方です。
伊藤 字を書いたりもするんですか?
加藤 字はちょっとだったら書きます。ローマ字だったらそんなに難しくないから。
伊藤 玲那さんもめっちゃ字を書く人で、もう完全にスタンバイしてます。
西島 今日はお話を聞くのでメモをとろうと思ってます。
伊藤 お二人今日はよろしくお願いします。少し経緯を話すと、玲那さんが東大の私の授業に来てくれたときに、玲那さんはVRを常に見ているとおっしゃっていたんです。その内容を文字起こしして、Facebookにあげたら、加藤さんが「けっこう近いかも」というコメントしてくれたんですが、それが私には意外でした。加藤さんは先天的に全盲ですよね。でも玲那さんは見えなくなって13−4年の中途障害で、VRが見える背景には、「見たい」という思いが強くあると言っていました。見たいから、いろいろな情報をキャッチして、それを視覚的に置き換えてイメージしている。途中で見えなくなった人ならではのものだと思っていたVRが、実は先天の加藤さんにもありそうだということが意外でした。
加藤 たぶんその、VRが発動する瞬間、想像するタイミングが同じなんだと思うんです。Facebookにあがっていた文章で思ったのは、駅の音がするから、ホームの形や方向をVR的に想像する、というのは同じだと思いました。ただ再生されるものはたぶん同じではないです。自分の場合には、見たことがある映像として再生されるのではなくて、歩いたりとか触ったりとかして構築していったものを、映像としてではなく、記憶の形として、3Dとか、模型的な形で、再生されるんですよね、たぶん。そういう違いはあるんじゃないかな。
伊藤 模型的ということは、触覚的ということですか?
加藤 全体を手で触れるものばかりではないから、触覚的というわけではないけど、歩いて覚えて距離とか幅とか…。
西島 なんとなーく分かるものもあるかもしれません。私も見たことなくて行ったことがある場所というのも時間の経過であって、たとえば極端な例だと、カナダのノートルダム大聖堂は、写真で見たらなんか見たような気がすると思うかもしれないけど、はっきっり見た記憶がないもので、中に入って、たぶん細かく言ったら湿度だの気温だの匂いだの、いろいろな視覚以外の「圧」だとか…
伊藤 圧?
西島 建物の圧とか。わかりやすく言うと、壁が近づいてくると、何か近づいてくる感じがするじゃないですか(自分が近づいているんですけどね)。
加藤 反響圧みたいな?
西島 そうそう。そういうようなものを、総合して、わあっと蘇る感じというのかな、と思いました。私の場合にはどうしても映像が勝っちゃうんで、自分から見た二次元の世界に置き換えるのが、一番簡単なんだと思うんです。なんだけど、すこーし、もしかしたら一緒かも、と思う部分は、見たことないという現実を受け入れたくないから見えるふりをしているんだけど、実際は建物に初めて遭遇したときのわあっという視覚以外の情報も、確かに呼び起こせるんです。ただ、どうしても、建物に入ったり、新しく経験したりすると、私の中で勝手に美しい建物を作っているんです。その時点でズレもあるし、現実と離れちゃうと思うんですけど、「視覚化したがりモード」が強いんで、そっちが勝ってしまう。でも視覚意外の記憶も確かにあるなあと思います。
伊藤 なるほど。加藤さんは、なぜ駅だとVRが発動するんですか?
加藤 駅に限らずですけど、音とリンクするんですよね。歩いているときは、音がきっかけで発動しますね。だから駅のホームから聞こえるアナウンスだったりとか、階段のところで鳴っている鳥の声とかがすると、こっちの方向にホームがあるんだな、とか思ったりする。あとは電車が来ると、走っていく方向と自分の位置関係を把握していったりとか、ちょっとずつアップデートされていく感じですね。それで明らかになっていく感じです。
伊藤 そもそも加藤さんにとって音ってどういうふうに聞こえているんですかね。加藤さん、白杖に鈴をつけているじゃないですか。杖をツンツンするのではなく、鈴の音で見ている。それってつまり、鈴の音を鈴の音として聞いていないということなのかな、という感じがするのですが…
加藤 そうですね。どうなんだろう。手を叩いたりとか、白杖バチバチといったことを単にしたくないだけで、鈴の音を自分のエコロケーションの発信源にしているだけです。
伊藤 そうすると、場所によって音がちがって聞こえますよね?
加藤 うんうん、それで反響すると、幅だったり壁があるかないかとか、天井の高さとか、階段がのぼりかくだりかとかは、わかりますよね。
伊藤 見える我々にとってのサーチライトみたいなものですかね。そっちに光をあてると、「あ、壁あるじゃん」みたいな感じで、そこに何かがあることがわかる。
加藤 結構暗いところで、ペンライトを持って歩いている感じと似ているのかもしれない。すると見たい方にペンライトを向けますよね。
西島 なるほど。
加藤 それと似たような使い方をするのは、パームソナーですね。あれは超音波が出るもので、ものに当たって跳ね返ってくるかどうかで判断しますね。すごく熟知している人は、パームソナーを使えば、模型を触らなくても形が分かるらしい。もっと昔はソニックガイドという眼鏡型のものがあったんですよね。耳をふさがないイヤホンのようなもので、顔を向けるとそっち方向に障害物があるかどうか分かる。
伊藤 なるほど。VRって「空間が出てくる」という感じがあるんですが、ペンライト的な見方からすると、加藤さんにとって空間ってそもそもどういうものなのかが気になります。
加藤 どっちもあって。さっき話した駅のホームが出てくるというときには、空間というよりは、ひとつの模型の塊みたいなものとして捉えていますね。「配置」ですね。「空間」として感じるときというのは、たとえばこの部屋に入ったときに、部屋の反響とか、前に来たときの記憶で奥に向かって長机があったよな、椅子があったよな、本がたくさんあったよな、といったことは空間として再生されます。でもその中の椅子とか机とかっていうのは「配置」なので、ものの位置関係として再生されます。「空間」と「ものの位置関係」というのは、たぶん別々に存在するような感じがしますね。
◎映像化が勝っちゃう
西島 へえ…すごく不思議な感じがします。私は極端にいえば、見えていたときのままなんです。話がずれちゃうかもしれないんですが、人はどういうふうに認識しますか?
加藤 人は…どうだろう
西島 あの、私の話になっちゃうんですけど、私は人や動物や建物の大きな差異がなくて、たとえばコンビニで買い物しているときに、ちょっと後ろにさがったら何かにあたったとしますよね。そういうときに、これは「目が見えない人あるある」だと思うんですけど、まず「人にぶつかっちゃった!」と思うから、「あ、すみません」と言う。でも実際はカートが置いてあったりするのが現実だったりする。私は何かカンっとぶつかったときに、振り返ったら、前傾したおばさんがいるんですよ。そのおばさんのかばんが当たったことになっているんですよ。ときに電柱にぶつかったときにも、私の中では、めちゃくちゃ背の高い外人とぶつかった、とかいうのが、目に入っているんですよ。「ほんとすいません」って言うんですけど、向こうがすごいいい人の設定のときもあれば、嫌な顔をしている設定もあって、相手がもののときは返事がなくてだいだい嫌な顔をされている体でいるんだけど、となりに夫がいて、「大丈夫だよモノだから」っていうようなことがあって、そのあと書き換えをするんです。
実際に人じゃなかったとしても、先にビジュアル化しているぐらい、映像化するのが早くて、勝っちゃってるんです。人でもモノでもなんでもそうです。「あ、誰かいるかも」「何かあるかも」って思うのとほぼ同時に、現れているので、加藤さんに伝わるか分からないけど、「見るのが先」なんですよね。それで、そのあとから、匂いとか声とかが入る。気配が勝っちゃうことも多い、確信がなくても。そういうビジュアル先行ですね。でも「体感」なんですよ自分にとって。
きっかけの何かは接触だったり匂いだったり音だったりして、先ほど音の話がありましたが、たとえばラーメン屋さんの匂いがすると、ラーメン屋さんが位置的に現れるんではないかと思ったんですよね。細かく言うと、音だけじゃなく、自分が知っている基盤、たとえば方眼用紙の上に立って、匂いやら音やらその日の天気とかの条件を加味した、すごーく細かい、複合的な要素のなかで組み立てられている部分も多分にあると思うんですよね。でも人に説明しようとしたときに「音」って言っちゃったほうが、すっとイメージされやすいだろなと思うから言っちゃう。
加藤さんのお話を聞いて、結構単純なことから組み立てされているのかなと一瞬思ったんですが、もしかしたら精度という意味では、私よりも「正確さ」が先行しているような気もしたんですよね。その情報がアップデートされていったり構築されていったりするときの情報収集の感覚とかって、ものすごい細分化・項目化していくと、けっこうおもしろいくらいたくさんあるんじゃないかと思っていて。私は中途なんで、そこが欠如しているところもあるかもしれないと思いました。なので、人間に会ったときに、顔がある、頭がある、服を着ているというような映像でイメージしているのか、「なにかいる」「なんかあるっぽい」くらいから、だんだん意図的に情報をもらいに行って(勝手に入ってくることも多いでしょうけど)、正確に認識されるのかなあ(習慣化されてるかもしれないですけど)、と想像するんですけど、どうですか?
加藤 いちばん最初の一瞬っていうのは、ものか人かという区別はなくて、なんかの「物体」なんですよね。その最初の瞬間というは、たぶん同じだと思うんですよ。ただ、柔らかいものか固いものかという情報は、自分から発する音からの反響音で先にとれるから…
伊藤 えっ、うしろに物体があったときでも、音が有効なんですね
加藤 はい。そこは自分で一歩下がったときの靴の音の反響で、後ろにいるのが人かものかはたぶん分かります。
西島 おお〜あらま。
加藤 もしくは、うしろに引いた白杖が当たって、それが固ければこれは人じゃないなと思うし、カチンと当たった音の響きで「いまのはカートだよな」とわかったりします。たぶん「当たった時のカートの音のイメージ」というのが勝手に作られているんです。でもコンクリートの壁だったら響かないから「カチ」という音になる。何かひとつの動作、アクションに対して、できていく、そこはアップデートじゃなくて構築ですね。
西島 音か…。
加藤 そのあと、人はそんなにベタベタ触るわけにいかないけど、カートだったらちょっと触れてみて、「あ、カートだった正解」みたいな感じになる。匂いもそうで、たとえばラーメンの匂いがしたら、カウンターがあって10人座れればいいかなというのを最初に想像して(笑)、でも入ってみたらもっと30人とかのサイズでテーブル席がいっぱいあるような店だったら「あ、ちょっと考えていたのとは雰囲気が違うな」というのはあったりする。
伊藤 けっこう丁寧に照合してますね。
加藤 してますね。
伊藤 玲那さんも照合はしてる?
西島 目的によりけりで。でもお話を聞いてると、「わたしけっこう適当だぞ」と思えてきました(笑)
加藤 伝えなきゃいけないからそういうふうに言ってるだけで、そんなに正確にはやってないですよ(笑)
伊藤 でも段階があるんですかね。見えていると、よっぽど見にくいものでないかぎり、いちいち照合するプロセスはない気がします。
加藤 分析したことないから分からない(笑)
伊藤 照合もちょっと違うのかな。
加藤 でも言われてみればそうかなという感じですね。
西島 いちいちやってると、5メートル進むのにすごい時間かかっちゃうじゃないですか。駅まで行くのに3週間とかかかっちゃうから(笑)、思い返してみればああいうことを頼りにしてるよねっていうことだと思うんですけど、でも勝手に想像してるんでしょうね。
加藤 してます。でもさっきなんで駅を例にあげたかというと、駅って基本形ってだいたい一緒じゃないですか。ホームがあって、線路があってっていうあるものと配置がだいたい決まってる。コンコースと線路が交差しているか平行かとか、ホームからコンコースが降りる階段か登る階段かとかそのくらいの違いで、基本の形はだいたい同じ。まずそこから思い浮かべて、いくつか今言った形のどれに近いかというのを読んでるんだと思います。でもすごい変わったのもときどきあって…
西島 無人駅とかね(笑)自動改札がポールのように立っててそこにタッチするやつあるじゃないですか。
加藤 はいはい。
西島 あれをふだん利用している視覚障害の人がいらっしゃるとしたら、どうやって覚えているのかなとおもっちゃいますね。まあ、そういうのが目新しくて面白かったりするんですよね(笑)
◎駅が一時的に手の中に
田中 加藤さん、人間を人の形として毎回思い浮かべてますか?
加藤 そこまで思ってないですね。それこそR2D2みたいな、円筒形の柔らかいもの(笑)っていう感じ。
伊藤 なるほど(笑)硬さ情報はけっこうでてきますね。
加藤 硬さは音で分かりますね。
伊藤 柔らかいR2D2が…
西島 ベイマックス的な?
加藤 その人が微動だにしなかったら、やわらかいポールなのか人間なのか分からないですよ。でも人間は絶対動くから、衣ずれや呼吸の音で、「あ、人だ」と分かりますね。そこで一応人の形には一瞬しますけど、それ以上する必要がないから、またもとの形に戻りますね。
西島 一瞬人の形にするんですね。
伊藤 「人だ」と思ったら人の形になるけど、そのあとは簡易化される…おもしろいですね。玲那さんは、人と話しているときに、相手の姿勢、たとえば肘をついているかどうかといった情報を細かくキャッチしてますよね。そういうことは加藤さんは意識していますか?
加藤 あんまりしてないですね。
西島 ほんとですか!
伊藤 じゃあずっとベイマックスと話している感じで…
加藤 (笑)よっぽど気になるときは考えますね。たとえば講師やっているときは、一応生徒の態度を記録しなきゃいけないからね。
伊藤 なるほど。モードのスイッチがあるというか、状況に応じてどこまで情報をキャッチするか切り替えがありますね。
加藤 そうですね。必要であればそういう展開はしますね。
伊藤 それは小さい頃から、だんだんモードを増やしていったんですかね。
加藤 そうですね。前に同じ先天の人で、環境をどうやって把握しているかというのをFacebookで書いている人がいて、「自分がその場に行かなくても、一時的に手元にもってこれるよ」と言っていました。さっきの駅の例にもどると、たとえば何十メートルか先にホームの音が聞こえたら、それはもう手の中にホームの形をした模型を一時的に持ってきてるような感じです。
伊藤 どういうことだろう…手の中で駅を回せたりする、ということですか?
加藤 そうです。ホームの形をした模型を手の中に持ってる感じです。
伊藤 それは子供のころから模型経験値が高いからなんですかね?
加藤 そうなのかな…。
西島 それは先天の人によくある話なんでしょうか?
加藤 どうかな。しっかり話し合ったことないけど、先天同士で話していると、ポイントとしては同じなのかなと思いますね。
伊藤 「イメージする」ではなくて「手の中にある」というのが面白いですね。
加藤 イメージってたぶん映像なんですよ。
伊藤 それもあるんですか?
加藤 自分はそれはないから、模型的というか、手の中にある感じになる。
伊藤 駅は大きいから模型になりますが、すごく小さいもの、そもそも手に入るものだと、その実物が手の中にある感じになるんですか?たとえば「クリップ」って言われたら…
加藤 あります。もともと手に収まるサイズのものは、そのサイズ感のままだと思います。
西島 超ちっちゃいものだとどうですか。微生物とか。
加藤 それは、逆に拡大しているんじゃないかな。でも顕微鏡で見ることはできないから、拡大した模型を触ったことがないと、想像はしないかもしれません。でもたいがい、たとえばノミやダニと言われたら「虫に似てるよ」と言われるから、昆虫として想像しますね。
西島 まったく無ではないけれど、近づけることぐらいはするということですよね。
加藤 うん、再現しようとはしていると思う。
◎触れないものの認識
伊藤 記憶が触覚的っていうことなんですかね。
加藤 そうですね。
伊藤 その記憶を組み合わせたりできるんですよね。
加藤 しますね。
伊藤 たとえば熱いコーヒーがコップにつがれていく音を聞いたときに、そんんなに熱いものがコップに注がれるところを触ったことはないけど、たぶん水がコップに注がれるのを触ったときの記憶と、コーヒーの匂いやコップの感触や湯気の情報とかを組み合わせて、「熱さについての情報」と「注がれることについての情報」が合体したものを作っているのかな、と思ったんですよね。
加藤 それはありますね。水って、しっかりした形としてはとらえられないじゃないですか。たとえば丸い蛇口から思いっきり吹き出していれば、水の形が丸くなるというのが外形から触ってわかるけど、そうでない場合もある。たとえば去年ディズニーに妻と行ったときに、ハンドソープがをガチャっとやると、ミッキーの形をした泡が手に乗るっていうのがあったんです。そーっと触ってなんどもチャレンジしたけど、くずれちゃって分からなかった(笑)。「ここが、たぶん、耳、かな?」みたいな感じで。
伊藤 前話してた、「髪の毛は触れるけど髪型は触れない問題」ですね(笑)
加藤 そうです、そうです、そういう感じ(笑)。ただ、デフォルメされた二次元のミッキーというのはいくらでもその辺にあるから、なんとなく分かったけど、全く触ったことがないと想像もつかない。
そういうのと同じで、注いで落ちて行ってる水の形がどうかというのは、あまり想像していない、あまり必要ないからね。注ぎ口の形から三角形なのかな、とか思うときはあるけど。
西島 必要じゃなければ、あえて想像していることも認知してないことが多くて。聞かれれば、「無視しているだけで分からないわけではない」ということもあるっていうことかな。
もしかしたら、熱いものを注いでもらったり自分で注ぐ音を聞くときに、私の場合は火傷が一番怖いので、コップのところに手をかざして、湯気を触ったりしていますね。重要度が高いものに持ってかれる気がします。
加藤 いま言われて気づきましたけど、そもそも湯気は形としてとらえてないから、それはもう熱でしかなくて…いま、湯気を表現した二次元の触れた絵を思い出そうとしてるけど、絶対ないとは思わないけど、あまりなかった気がします。湯気がどういう形に見えているのかっていうのは、表現されているものが出てこないですね。それは熱としてしか感知してないんだと思います。
田中 加藤さん、揚げ物とかやるじゃないですか。音だけで揚げ物作る感覚がすごく理解できないというか…
加藤 揚げ物は、そうですね、音が変化していくから分かりますね。一回大きな音がして、そのあと一回静かになって、もう一回また音が変わる。
西島 音だけで揚がったことを判断するんですか?
加藤 揚がった、というのは分かりますね。
西島 私はまだ未熟だな(笑)私は箸でつついて、浮かんでくる感触で判断しますね。
加藤 ああ、それも使いますね。あと、浮いてきたときに菜箸でそっとつついてみると、振動しているのが分かりますね。
伊藤 料理は二人とかなりするんですね。
西島 (小声)さいきん、しなくなった。結婚する前のほうがしてた(笑)
加藤 やらない人が家にいるからね(笑)
西島 ぎくっ(笑)
加藤 まあ、好きだからやってますよ。食べるのは揚げ物が好きだからやりたいんですけど、片付けが手間なので、いまはクックパットとか見ながらいろいろやってます。最近うまくいったのはキッシュですね。
西島 しゃれおつ!
加藤 パイシートも買ってきちゃうし、全然ちゃんとした作り方じゃないんですけどね。
伊藤 料理は確かに音で判断しますね。
加藤 このまえ、2週間くらい、風邪をひいて鼻がきかなくて、料理をしてても何を作ってるか自分でも分からなくて(笑)。さすがに妻から「いつもと味が違う」と言われましたね。
◎世間的に…
田中 さっきの話にちょっと戻るんですけど、加藤さん、映画の音声ガイドのモニターをよくやっているじゃないですか。音声ガイドだと、人が落ち込んだときにどういう仕草をするとか、わりと描写が多いじゃないですか。そういうのは、ふだんの生活のなかではつながっていかないんですか。
加藤 つながっていかないんですよね。音声ガイドは、どんな人が見てもわかるように作っていかなくちゃいけないんですよね。乱暴なことを言ってしまえば、ストーリー的にその表情があまり関係なかったら、ガイドは自分にとってはじゃまなものになる。「いま嫌な顔をした」というのがストーリーにとって必要なら入れてほしいけど、俳優のアドリブや監督の意図で一時的に不思議な顔をしたというのであれば、必要ないなと思ってしまう。ふだんも「いま嫌な顔したかな」とか考えようと心がけてはいるけど、あんまり気にしていない。
伊藤 その加藤さんの基本的な「断捨離モード」が気になりますね(笑)。必要ないものはあるけど捨てられる、そして大事なものにフォーカスできる。玲那さんは、それもあるけど、どんどん足していく感じで、そこはやっぱり違いがあるのかなあと思いますね。
加藤 表情だったり色だったり、そういったものを想像するのは、自分にとっては倫理観みたいなもので、世間的にそこは気にしてなきゃいけない、という感じですね。だって自分が着る服とかが、あまりにも上下あってなかったら、そのままでいていいわけないなと思うからね。昔から、母がうるさかったんですよね。
田中 別の先天の人も、テレビに出る機会があって前日にお母さんから電話かかってきて「見えないからって変な服を着ていたら、ああ見えない人はやっぱりおしゃれじゃないのねって思われるからおしゃれしてきなさい」と言われたって言ってましたね。
加藤 それはもう、うるさく言われてましたね。
西島 あります。すごくあります。
加藤 あるね。あるっていうか、実はない気もするんだけど(笑)
伊藤 (笑)
加藤 実はないんだけどあることにしてるっていうか。
西島 そうでないとやっかいなんですよ。
加藤 そうそう、あとあとやっかいになる。
西島 要は持ってるものを、見えている人は意図的に出す必要がないんですよ。たとえばファッションが得意な人は、それを披露すべき場所で披露すればいいと思うんです。でも自分の場合は、色感覚とか、持ってるけど大事じゃない感覚を組み込んでおかないと、もうそういう能力がないんじゃないかと決めてかかられたりする。そうすると、のちのちほかの能力もないんじゃないかと思われたり、それを言うこと自体が差別なんじゃないかと思われて聞かれないんじゃないかとか、そういうやっかいごとを回避するために、一応(色感覚が)ありますよっていうことを、示しておく。親は余計に心配するのかもしれないですね。お母様の気持ちは分からないですけどね。でももしかしたら本当はできることがいっぱいあって、(見えない人と)一緒に暮らしたことがない人は、想像もしないだろうと(お母様が)思われて、そういうアドバイスをするのかなと思います。
加藤 ギャップがあって。妻は晴眼者なんですが思った以上にそのへんに無頓着なんですよね(笑)むしろ、私のほうがうるさい。妻はぐちゃぐちゃでしわしわのシャツとか着て出かけちゃう人だから、それを私が恥ずかしいから止めてくれと言ってる(笑)。
伊藤 玲那さんのだんなさんはそのあたり、気にするんですか。
西島 はい(笑)。「その格好でいくの?」って警告ランプがつきますね。
加藤 結局そういうふうに思われるのが面倒だなと思ってしまうから、それはできるだけ、違和感のないようにはしておこうかなと思ってる。
西島 それはすごーくわかる気がします。
◎そもそもVR
伊藤 ちょっと話が戻っちゃうんですが、さっきのVRの話で、そもそもVRをどう理解されているのかが気になりました。そもそもお二人ともVRを体験したことないわけですもんね。
加藤・西島 ないですね。
伊藤 それでVRと言われてすっと「VRみたいだ」って言えてしまうことがすごく不思議ですよね。
西島 私はVRを知ったきっかけはラジオの説明でした。ゴーグルをかけると、たとえば今自分の部屋にいても、お城のなかに「いる」っていう様子が見える、と。それで右を向いても左を向いても上を向いても見えて、平面の画面が目の前にあるのとはちがって、その空間に入ったっていう疑似体験ができる、と。なおかつ、体験した人が「VR内で、子供がキムチを持って近づいてくると、なんかキムチの匂いもする気がする」ということを言っていたんです。それぐらい、その中に急に移動したような錯覚を感じる、と。いちばん最初にこの説明を聞いたときに、いま私が見ているものはまさにこれだぞ、と思ったんですよね。
伊藤 おそらくVRが出てきた最初期ですね。
西島 そうですね。それまでは、自分がいまどういうふうに人と目をあわせているのかとかを説明するのも難しかったんですよ。自分のなかでは、なんとなく人の顔を作って、目線も作って、目線が動いたことを想像して、そっちを向くように、目をみたつもりになっているだけなんだけど、VRという技術が出てきたことで、自分の置かれている状況と、ゴーグルをつけた晴眼の人が似ているんじゃないかなと思ったときに、分かってもらいやすい、というのがありますね。正確にVRを体験したことがないので、どれほど自分がやっていることと近いか照合できにんですけど、体験した人の感想と、自分の持っている感じは、確かにすごく似ていた。
伊藤 単なるビジュアルじゃなくて「キムチの匂いがするような気がする」とか、そういうことが大きかったんですかね。
西島 それくらいの臨場感がある、ということですね。実際嗅いだかどうか分からないし、本人は嗅いだはずがないという認識もあるのに、リアルだ、という言い方も含めて想像しやすかった。見えてたまんまだろう、というところですね。
伊藤 加藤さんはVRをどこで知ったんですか。
加藤 いくつかあって、最初にVRってなんぞやというのを思ったのが、ジョイポリスに行ったときに、「臨場感あふれるライン下り」みたいな、ボートに乗って遊ぶアトラクションがあって、自分はジェットコースター的なものが好きだから、乗ってみたんです。乗り物がちょっと傾いて、前から風が来て、水しぶきがちょっと飛んでるだけ、それなのにみんなキャーキャー言ってて、自分は「なにが?なんで?」って分からなくて。最初にゴーグルを渡されたから、これをかけているとそういうふうに見えるんだろうな、くらいの感じでした。
伊藤 説明なしで実際にVRをやっている人がいる、というのが最初だったんですね。
加藤 何だか分からなくて。視覚的効果からもたらされるものなんだろうな、くらいの理解しかなかったです。それで、いろいろ体験した人の話を聞いていると、ホラー映画とかを見ていたときも、実際に、自分の顔の前に血しぶきが飛んできた気がするとか、ちぎれた手が浮かんでいる感じがするとか言っていて、あ、そういうことかとわかりました。「本当にそのなかに自分がいる」っていうことなんだなと思いました。それが少し分かったあとくらいに、『インナーヴィジョン』という映画に出演して、バーチャルカメラというのを使って説明されたときに、その映像の空間の中に自分がいてそこでカメラを持って写しているという感覚ですと言われて、そこでなんとなく理解ができた気がしました。それで(生活のなかで)音や匂いから再生されるVRっていうのは何なのかというのを考えたときに、さっき言ったように、模型を手元に持ってきて、駅なら駅の模型の中に小さい自分のフィギュアを置いて、どのへんにいるか、というのを考える。だからその「小さい自分」がVRの中にいるという感じですね。
伊藤 加藤さんがその「小さい自分」の視点になれるということ?
加藤 なれる。
伊藤 なるほど。じゃあその「小さい自分」の視点から、一人称視点で、駅の改札を通ったりできるということですね。
加藤 そうです。それが、全体を理解しているんだけど、改札口を通る瞬間は、改札口のミニチュアと自分の小さいのがいて、改札口を出たら、またその先何メーター分かを切り取ったコンコースの通路だったりというのが、ちょっとずつスクロールしていく。
伊藤 自分が前に進むからスクロールしていくんですよね。部分部分に分かれていて、つながっていない感じなのかな。
加藤 でも全体は全体で呼び出すことはできます。
伊藤 なるほど。呼び出せはするけど、ミニチュアVRの中では、意識していないということですよね。
加藤 そうです。たとえば「今日はいまから大岡山に行くな」となったら、一回駅の構造を全体的に呼び出します。でもたとえばホームから上がって改札まで行くとなったら、そこしか歩いたことがなくて、コンコース全体の形を知っているわけではないから…。
西島 自分が知っているルートや、そのルートにかかわる壁や自動販売機の配置、自分が経験したものと関わりのあるものは、いっかい離れても、模型としても見れるし、そこに立って「右側に〇〇がある」という捉え方もできますよね。
加藤 できます、できます。今日ひとつアップデートされたのは、大岡山の改札の横にローソンがあることで、ぼーっと待ってたら後ろでコンビニの音がして、ローソンのCMが聞こえたから「ここにローソンがあったんだな」と思いました。
西島 ローソン建ちましたね(笑)
伊藤 逆に見えている人でも何を思い出しているのかと言われると難しいですね。渋谷に行くとなったとき、駅の全体像は必ずしも理解していない気がします。
◎となりにいる人のように見たいor自分は自分
伊藤 玲那さんはVRに関して作者側にもなりますよね。けっこう自分で作って、作り込んでいくところがある。この前話していたのは、夕方でセラフ(犬)のトイレが見にくいときに、街灯を立ててまわりを明るくしたりすると。そういうことは加藤さんにもあるのか、なかったとしても聞いたときに「それも便利かも」と納得可能なものなのか、気になります。
加藤「便利かもしれないな」というぐらいかな。
西島 あ、便利かもとは思ってくれるんですね(笑)
伊藤 じゃあVR内で音を鳴らしたりするんですか。
加藤 ありますよ。それはたぶん、駅のホームに常に鳴っている音、たとえば階段の位置を示す鳥の声とか、ホームの蕎麦屋の換気扇の音とか、近くにある店の音楽とか。
伊藤 「ここをもうちょっと知りたいんだけど」というときに、ありもしない音を鳴らしてみたり、ここに音があったらいいなというところに配置してみたり、ということもありますか。
加藤 それはたぶんいったことない駅にこれから行く場合ですね。もともとあった駅の形というのを一回呼び出しておいて、こんな形かもしれないな、というのが自分にとってのVRかなと思います。
伊藤 なるほど、その全体を構成する断片の情報というのは音を使って拾った情報ですもんね。
加藤 はい。何種類か、たとえば「島型ホーム」「対面型ホーム」とか、これだといいな(笑)、というのがあって、それでホームから階段を呼び出してきて、組み合わせて想像しますね。
伊藤 玲那さんはけっこう現実と離れていく自覚もありながら、作り込んでいくことがありますね。
西島 この前街灯の話をしたときに、亜紗先生に「全体を明るくしないんですか」と聞かれて、「その手があった!」と思いました(笑)。なんで現実の夜というものにとらわれていたんだろう、昼間にしちゃえばよかったんだ、と。でも、街灯も自分でつけようと思ってつけたというよりは、見づらいなと思ったらついた、という感じのほうが近いんです。ある意味、「夜を昼にする」よりも「夜に街灯をつける」ほうが、自分の目の記憶のなかで、リアリティがあるのかもしれないです。
伊藤 部屋が暗いときに電気をつけるような感じ?
西島 そうです。夜を昼にする魔法を使った経験はないので(笑)。でもその手があった、と思って意図的に試みてみたんですけど、ちょっと時間がかかるんですよ。「昼間」と思って、意図的に映像を作ろうとすると、昼間っぽい音とか探したくなっちゃうんですよ。それを作る材料を探そうとしちゃって、「どう考えても昼間のあたたかさではない」とか、そういうのが勝っちゃって、ちょっと時間をくったんです。だから勝手に想像するものっていうのも、何か意味というか、きっかけがあるんだろうと思うんですが、消費カロリーゼロで見やすくするのは、たまたま街灯だったのかな、と。
伊藤 なるほど。勝手に作っているように思うけど、実はちゃんと理由があって、過去の経験とかから考えて突飛じゃないやり方なんですよね。
西島 そうです。街灯が「にゅっ」と生えてくるというよりは、その光さえあればいいというのが一番優先です。せっかく光あるから、街灯つくっちゃおうかな、というのがあります。私の中でのライトは古い街灯という感じで。でも朝起きて外に出ると、もうそこにはないんですけど。加藤さんと私が一番違うなと思うのは、不必要なものを作りたがりなところですよね。
伊藤 その違いってどこから来るんですかね。
加藤 そもそも自分にとって光は必要ないからそこが違うのかな…。だからVRというか、位置関係とか空間を再生させるためには、そこには光っていうものは関係ないので、重要ではないのかもしれない。ただ、朝昼夜で環境音っていうのは違ってくるから、時間経過っていうのはデータとして構築していっているんだとは思うですけど。
伊藤 加藤さんは絶対的な時間ではなくて、何メートル歩いた、どれだけ時間が経った、というような変化量で捉えている感じがします。
加藤 変化量…
伊藤 玲那さんは、わりと、外がいまどうなっているか、つまりまわりの人と共有できる状態であることを重視しているように思います。
西島 ときどき照合したくなりますね。自分が感じた変化量と相手が感じてるものが同じか。たとえば亜紗先生といっしょに歩いていて、亜紗先生が目で見て5メートルなら5メートル進んだっていう景色の変化と、自分が感じた変化を、ポイントというよりは流れで、確認、確認、しながら作りたがりなんですよ。それが大きく離れることに、リスクを感じているからそうなんだと思います。何かを得ようというより、リスクを回避したい、ずれていることが居心地が悪いんだと思うんです。距離が近い夫だと、ずれててもいいし、いっしょだったらなお楽しいという感じだけで済むんですが、そうじゃない人とだと、ずれたから何、という想像まではしてないけれども、ずれがなるべくないように、という感覚はあると思います。
伊藤 自分のまわりにいる人と同じ情報や見え方に合わせたいということですよね。
西島 そうですね。確認の意味もあると思うんですけどね。だから一緒に歩いていても、同じ方向を見ていたいんです。仮に見えていなくても、つまり捉えられなかったとしても。亜紗先生と並んで歩いていて、亜紗先生が右を向くと、自分も右を向きたくなるんです(笑)。いっしょの動きをしてる。それをずっと続けてると、亜紗先生はきっと何を見ているのかという情報も集まってきて、映像が華やかになってくるんですよね。横断歩道とか渡るときも、亜紗先生と自分が並んでるのを外かた見たら、右、左、右って動きがリンクしてると思います(笑)それがなんかすごく居心地がいいんですよね。
伊藤 加藤さんはそういう感覚はありますか?
加藤 すごくそれを目指した時期はありました。でもすごく乱暴な言い方をしてしまうと、それは無駄だと思ったんです。それで、自分の肌とか耳とかでとらえたことを見えている人に伝えればいいかな、会話で伝わればいいかなと思いました。だからやめました。
伊藤 いつごろやめたんですか。
加藤 十代の、思春期のころですね。自分にとってみんなと違うことが恥ずかしいと思っていたから。鉄道ファンだったんですけど、何色で何系で、ということも全部耳で、モーター音とかで捉えていたのに、見えているかのような言い方をしていたんです。オレンジのあれでどうで、というふうに仲間同士で話していました。でもそうやっていることは無駄なんだなということに、ふと気づいたんです。だったら自分はモーター音で理解しているんだよ、ということを明かしてしまえば、そういう楽しみ方もあるのね、ということもお互いに分かり合えるということが分かって、だったらそれでもいいんじゃないかな、と思った。
伊藤 玲那さんはそのへんはどうなんだろう。
西島 ギク(笑)
加藤 ああ、否定するつもりで言ったんじゃないです(笑)それはそれでいいと思います。
西島 分かります、分かります。何というか、何でしょうね。
伊藤 玲那さんは、もともと見えていたから、基準が違うよね。
西島 絶対経験みたいなものは大きいと思います。
加藤 それはあると思いますよ。「明るいから暗い、暗いから明るい」ということを自分はいつも言ってるけど、見た経験があるということは、暗いところに行ったら視覚的に捉えられないからあかりが必要だよね、ということは至極当然に思うことであって。
西島 途中から、しかも私も思春期のときに急に見えない人になったから、すごくやらなきゃいけないことに追われている時期で、効率よく、私からすれば残った能力を使っていくか、という課題がありました。もともと見えない人だったら知っていてできることを、自分は、聞いて、知って、やって、できる、までの段階を踏まなきゃいけないし、心もちょっと折れる。とにかくやらなきゃいけないことが急にふえる中で、それでも効率化したいと思っていた。だから加藤さんが「無駄で、必要ないんだ」とおっしゃるとき、ほんとにそのとおりなんです、と思う部分がすごくあるんです。で、実際に意図的に自分が何かを確実にこなそうと思ったときは、効率化優先になるんです。自分の感覚のうち100パーセントに寄せて信用できるもの、たとえばスポーツなどに力をかけていました。
でも勝敗や自分の利害から離れちゃったりすると、効率化があとまわしになってしまって、余談のほうが面白くなっちゃったりする。よくもわるくも両方の世界を知っていて、忘れたくないんですよね。亜紗先生が見ているというものと、自分が見ているものがずれていくのが、きっと悲しいんだと思うんです。だから合理的なものじゃなく、自分の気持ちを満たすものであって、必要性の有無というのはあんまり重要じゃないのかもしれないですね。
加藤 それは絶対忘れないようにしてもらったほうがいいなと思う。ぼくらからすれば、それはうらやましいことで、少しでも見た記憶を持っているということは、「あざやかな赤」とかって言われたときにぱっと想像ができるわけで。赤とか青とかって言われても、自分にとっては単なる記号みたいなものだから、あざやかかどうかなんて知ったこっちゃなくて、そういう想像が容易にできないことは、やっぱりちょっとつまらないなと思うこともある。そこはすごく大事にしてほしいなと思います。
西島 ありがとうございます(ペコリ)。
加藤 何をえらそうなこと言ってるんだか分からないけど(笑)
◎妄想をつくりこむ
西島 まだ映画(『ナイトクルージング』)を拝見させてもらってないんですけど、人が見るものを作るというのは、一時的にでも私みたいなのがうらやましいって思ったりします?
加藤 思います、思います。想像もしていなかったんですけど、「自分はこういう映像にしたいんです」というのをすごく一生懸命説明して、最終的に理解してもらったら、「そんな映像はもう存在するから作ってもつまんないよ」って言われて。いや知ったことかよ(笑)
西島 なるほど(笑)自分が想像したものを伝えたとして、向こうも分かったって言ったとしても、伝わっているかどうか分からないですよね。
加藤 そうそう、そこに絶対の保証はないですよね。その二方向からイラっとしました(笑)楽しかったですけどね。
田中 さっき玲那さんが、「想像する印象を華やかにしたい」とおっしゃっていて、そこには見える/見えないとは違う価値観がまたあるんだろうなと思いました。
加藤 映像的な華やかさという意味なんじゃないかなと思うんだよね。自分にとって、必要かどうかというのをさておいて考えると、華やかにしたいと思っているんだとしたら、駅とかでへんな匂いがするよりはパンの匂いがしていたほうがいいとか、そういうふうには置き換えられる気がします。
田中 加藤さんは、そういう妄想とかしないんですか?
加藤 ありますよ。あるある(笑)
田中 これまでの話だと超ミニマリストみたいな感じになってるけど(笑)
加藤 必要かどうかということそうでもないということで。
西島 とくに家の外に出て、「動く」ということが伴うと、必要性とかを考えていかないと、現実問題として危ないですよね。私みたいにいつもいつも妄想しているのは、夫がとなりにいるから気楽なんです(笑)。妄想しているから、縁石だよって言われて乗っかって調子に乗ってポンておりたら水たまりにはまったりするんです(笑)。
加藤 遊びに行く時のシミュレーションとかをするときには、そういう妄想みたいなのはあると思います。結婚する前は、どこでデートしようかなとか、けっこう出かける前に考えていたと思います。そんなの何でいましゃべんないといけないんだ(笑)
伊藤 え、それで?
加藤 (笑)たとえば海辺でデートするとしたら、自分は海の音とか好きだし、映像的というよりは音的に妄想してたんでしょうね。こっちの道から行くと、話しながら歩くのに自分的には雰囲気がいいよねとかシミュレーションして、でも食い違いがあったりする。相手は見えるので、景色がきれいだからあっちから行こうと言われたり(笑)景色がいいほうに行くと自分にとっては高速道路の横でうるさいだけだったり。
伊藤 そこでイメージ付け足したりしないんですか?
西島 いいタイミングで船が「ボーン」って言ったりとか(笑)
加藤 します(笑)
西島 そういうのが多分、私でいう「光をたす」みたいなことなんだと思います。
加藤 背景、バックグラウンドみたいなものなのかなと思います。遠くに聞こえる音。それは映画を作る時にすごく思っていました。
伊藤 映画を作る作業って、言ってしまえば「華やかにする作業」ですもんね。
田中 でも加藤さんは、あえて岩山を背景に選んだりして、書き込むということが難しいから、シンプルにしてましたね。けっこう削っていく作業が多かったなと思います。クリエーター側がすごく効果的なものを作ってきたとしても、加藤さんは「映像としてはそうなのかもしれないけれど、必要性がわからない」とカットしたりしていましたね。ビジュアル的なエフェクトは切っていった。でも音は、「自動ドアが開く音がしたんだったら、閉じる音もするべき」とか合理性にもとづいているなと思いました。
加藤 意外とそこいい加減にやっている作品が多いんですよね。受話器とったけど置いてないじゃん、みたいな(笑)。
田中 だから音も華やかにするというよりは、わりと合理性にもとづいていたような気がします。
加藤 時間がもっとたっぷりかけられたら、やっていたと思う。
2020年1月22日東京工業大学大岡山キャンパスにて