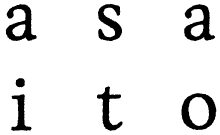半谷さんは視覚障害者柔道銀メダリストの求道者。動きを習うという過程には、身体Aから身体Bへの翻訳が伴う。晴眼者の場合には、その翻訳過程が視覚情報と社会的コードによってかなり自動化されているけれど、それが使えない半谷さんの場合、マニュアルの翻訳や自覚されていない要素の意識化が必要になる。半谷さんの圧倒的な言語化能力だからこそとらえられるものがたくさんあり、と同時にどう支援できるかも考えさせられるインタビューでした。
半谷静香(はんがい・しずか)さんプロフィール
1988年福島県生まれ。網膜色素変性症により幼い時から弱視で、兄の影響で中学から柔道を始める。パリパラリンピックにて、視覚障害者柔道女子48キロ級の銀メダルを獲得。トヨタループス株式会社所属。
◎答えを感じとるor無限の計算式
半谷 福島のいわきのメカリチョコ、お土産にどうぞ。いわき生まれ、いわき育ちなんです。
伊藤 ありがとうございます!いわきだと震災のときは大変ではなかったですか?
半谷 震災よりも、2019年の台風19号のときに川が氾濫して、家が沈みました。地震のときもそれなりにぐちゃぐちゃになりましたけど、どっちかっていうと氾濫した方がすごかったですね。冷蔵庫が浮いていたと聞きました。
伊藤 えっ、大変でしたね。しばらく家に住めなかったですよね。
半谷 しばらく帰ってくるなって言われましたね(笑)。氾濫したときは、自分の拠点は東京で、東京で合宿してました。こまめに実家に電話して、 8時の時は大丈夫だって言って、お父さんはお酒を飲んでたんですけど、 10時になったらもうだめだってなっていて。暗かったから水位が把握できなかったみたいで、もう家電も全部だめになりました。視覚障害があると、家にいなくて本当によかったなと思いますね。震災のときは大学生だったんで、そのときも家にいなくてよかったなと思いましたね(笑)
伊藤 けっこう強運の持ち主ですね(笑)
半谷 (笑)本を読ませていただいたんですけど、めちゃくちゃ勉強になりました。
伊藤 いや、そんなことないと思いますよ(笑)
半谷 いや、本当に勉強になりました。というのは、障害の程度によるクラス分けのルールが変わって、全盲の選手になったので、練習方法も今までと同じじゃだめだなって思ったんです。そのときに、伊藤さんの本に出てくる葭原滋男さんの文章を読んで、自転車のタンデムをしているときには、前を漕いでる選手に重心を乗せるんだ、っていうフレーズに出会いました。それで、柔道もまっすぐ立っているだけじゃだめなのかなと思って、乗りにいくようにしたら、コントロールできるようになったり、相手が「見える」ようになったりして。
伊藤 見える?
半谷 そう。本の中にも「見える」という書き方があって、確かに見てるのと一緒かっていう発見があったから、今があるというか。
伊藤 なるほど。うれしいです。すみません、まず基本情報としては、もともと弱視だったということですよね。
半谷 そうです。幼少期から0. 07とか、0. 08ぐらいの視力しかなくて。そのあと目が良くなったわけじゃないんですけど、目の使い方がリハビリでちょっと固定できるようになったりして、高校3年生の時が一番視力のピークで0. 09出ていました。でも大学に入ってちゃんと勉強するようになったら目が悪くなりました(笑)
伊藤 高校までは盲学校に通っていたということですか?
半谷 いや、一般の高校に通っていて、大学から筑波技術大学に入って、4年で卒業して、25歳の年に福島県立盲学校に再度入学しています。
伊藤 じゃあ、見た記憶はある?
半谷 あるんですけど、でも晴眼ではないので、ちゃんと見ていたのかが謎です(笑)。 色があんまりわからないので、色弱です。お医者さんからは色弱なわけがないって言われて、 色を当てるトレーニングをずっとしてたんですけど、 それが人生の中で一番苦痛でした(笑)。 家でもずっと折り紙並べられて何色か当てるまでやらされたんですけど、つらすぎでした。
伊藤 なるほど、実感としては色は分からないということですね。
半谷 なんとなく、原色だったら「赤」とか「オレンジ」とかが横に並んでる状態だったら、 斜めにすると分かることがあるんですけど、ぱっと前に出されたのが何色かは全然分からないです。
伊藤 今、実感としては、一番情報収集に使っている感覚は何ですか?
半谷 何だろう…私生活では多分、音ですね。柔道では、多分、体性感覚のほうだと思います。
伊藤 その場合の体性感覚っていうのは、体の傾きってことですか?
半谷 そうですね…関節位置覚とか重心の移動とか、圧ですね。 圧っていうのは… 圧ってなんだろうな…柔道って襟とか袖を持つので、その釣り手と引き手にかかる圧の変化で、相手の重心の位置を感じとるんです。
伊藤 ああ、手で感じとるんですね。
半谷 子供と歩いてたりおばあちゃんと歩いてたりすると、どのぐらいの速さで歩いているかって、手に伝わってくるじゃないですか。あの感覚と似てますね、柔道って。
伊藤 柔道の場合、柔道着を掴んでいる手は、力は入れているんですか?
半谷 それね…今の私のテーマなんですけど、基本的には力を抜くんです。抜かないとやっぱり感じ取れない。でも抜きすぎると完全に負けるのですよね、相手の力に負けて。そこの境目を探すんです。相手の力を感じていて、でも自分のペースで動きを作る。この境目を探しています。
伊藤 盲導犬を使っていた友達が、ハーネスをギュッと持つと何も分からなくなるけど、持つ手を緩めると、盲導犬の顔が右を向いたとか、そういうことまで分かるんだって言っていたことを思い出しました。だから盲導犬を持っている方の手はなるべく受け身な状態にしておくのがすごく重要だと。でも柔道の場合は、そこに「勝つ」ということも両立していかなくちゃいけないわけですよね。
半谷 今の「受け身」っていうワードがすごい良いなと思いました。でも、ただ触っているだけだったら、それでいいんだけど、 たとえば子供と手をつなぐときなら、転ばないようにするときにちょっと引き上げますよね。ああいう手の使い方が、柔道の攻撃の手と似ているんです。強すぎたら相手が転んじゃって自分がしたいことができなくて、相手の次の足を誘導するための力の入れ方を、 相手の力の向きを感じ取って、キュッてやるのが柔道、らしいんですよ。らしいんだけどたどりつかなくて(笑)。 試合ってなったら、そんなことも考えなくても良くて、強引でも勝てば勝ちなんで。例えば、一試合目で緊張しちゃって、力が抜けないってなったとする。ま、だいたいそうなんですけど、きれいな柔道、理想の柔道はできないけど、 勝たないと決勝にはいけないっていう時は、もう強引でも何でもいいから、力でねじ伏せちゃうこともけっこうあって。
伊藤 そっか。勝負の世界だったら「勝ち進む」ってことを考えなきゃいけないから、とりあえずこの試合勝つぞってなったら、理想系じゃなくても力でやっちゃいますよね。
半谷 柔道は勝てば強いってなるんで、試合時は手段を選ばなくていい。でも練習でそれをやってたら強くなれないんで、こだわって練習します。この間のカザフスタンの世界選手権は合計で5試合しているんですけど、全部フルで出し切ったら5試合はとうてい持たないんです。試合を早く片付けたい時は、強引に行ったり、今だと思ったタイミングでねじ伏せたりっていうことも起きたりします。
伊藤 5試合持たないっていうのは、集中力ですか?それとも体力?
半谷 握り続けるので、前腕がやっぱり辛いです。見てると何もしてないように見えるじゃないですか。でも、すんごい握り合ってて、手首を立てなきゃいけないんですよ。試合が終わると手が何も握れなくなるんです。試合の日はペットボトルの蓋は開かないです。
伊藤 そうなんだ〜!
半谷 柔道、難しすぎて訳わかんないですね。
伊藤 奥深いんですね。
前に晴眼の方で柔道をやってた人の話を聞いた時に、柔道って技そのものよりも、技に行く前のストーリー作りがすごい重要っておっしゃってて。こう来てこうなるっていう道筋に相手を向かい入れるみたいなイメージだと思うんですけど。
半谷 もうおっしゃる通りです。でもそれが、見えないがゆえに、そのモーションを知らなかったりするんです。技の起こりがあって、崩しがあって、作りがあって、かける、までがあるんです。相手の重心をまず「崩す」ところから始まるんですけど、崩すまでの誘導が「起こり」、重心が崩れた後に背負い投げとか大外刈りとかっていう技の形を作る。この「作り」っていうのが、普段私たちが基礎練習でやってる「打ち込み」って言われる練習で、技をかけるまでの形を作ります。で、「掛け」が、足を掛けたり、手を持ってきたりして掛けて、最後「投げる」に至るんです。
でも、私は前半の部分をずっと知らなくて。東京パラまでやってきて、見えなくなって、今の新しいコーチについて来てから、「そんなじゃ勝てない」って言われて、崩しとかの練習し始めたら、 柔道ってちょっと面白いじゃんってなって(笑)。
伊藤 ただの力じゃないってことですね。
半谷 そう。コーチのテーマが、 「力の通り道を感じる」だったんです。柔道を別な言葉で表してってお願いしたら、コーチは「畳の上のサーフィン」って言うんです。
伊藤 え、そうなの、超意外なんだけど…そうなんですね。
半谷 コーチに聞いたら、一人よがりで思いっきりやっても掛からないから、波を感じて、力の向きに合わせて体を調整するのが柔道と似てる、って。それに対して自分が答えたのは「無限の計算式」で。
伊藤 だいぶ違いますね。
半谷 自分は、テコの原理で柔道を観察してきたので、 三角形を体の中にいっぱい作ってて、三角形の線の延長線上の交点に足を置いて投げるとか、そういうふうに考えてきたんですね。だから計算式だったけど、コーチは、そんなこと言ってないでちょっと感じなさい、と。というわけでサーフィンを始めました(笑)。
伊藤 なるほど。じゃあ全然タイプが違うコーチだったんですね。でもたぶんすごい学びがありそうですね。
半谷 お互いにたぶん学びはあって、本人ももともとは言語化をあまりしない人だったけど、私が納得できない練習は絶対やらないタイプなので、言語化してくれるようになりました。
伊藤 すごくいい関係ですね。実際にサーフィンやってみて「これか!」って思いましたか?
半谷 思いました。それまでは、触って、位置を確認して、自分は曲がってるんだよとか、 既存のものにこっちが合わせに行かなきゃいけない感じだったんです。でもサーフィンは、ボードの上で自分が立てる位置を探したり、体の真っ直ぐを探したり、推進力と自分の立つ位置とボードの傾き感、それを考えながら、正解をただ探すだけなんです。だから答えは自分の体が知っている。答えは自分の外にではなく、中にある。あとは、そうだ、気持ちいい感覚が正解。自分がやりたいと思った動きが正解っていうことは、どの競技でも多い、と思いました。
伊藤 なるほど。計算式の考え方だけど、こうやるべきっていうゴールが外にあって、そこに自分を当てはめてく、流し込んでく、みたいな感じだけど、サーフィンはボードから伝わる波の動きとの関係でさぐり合って、ここが正解だって感じとる。そしてそれが気持ちいいっていうことですね。
半谷 失敗したら落ちるだけですからね(笑)。それを知ることができたのが一番大きかったです。
メールにも書いたかもしれないですけれど、自分はもともとその三角形で考えてたんで、テキストを作りたいと思っていたんです。でもそのテキストは、全員が同じ方法で同じものを目指せるんじゃないかっていう考えなんですよね。体育のテキスト、カリキュラムがあるように、 視覚障害者が物事、動きを学ぶための触り方とか聞き方がマニュアルになったら効率的だし、 指導者と当事者がすれ違いにならなくて済むんじゃないかなって思って、テキストを作りたいんです。けれど、サーフィンに出会ってからちょっと難しいかもしれないなって思い始めました。
伊藤 なるほど。テキストがあったとしても、それは正解を示すテキストじゃなくて、ひとりひとりが自分の正解に辿り着けるようにするための、考え方とか道筋みたいなものが書いてあるんですかね。
半谷 そうかなって思いました。 テコの原理でみんなに説明したら、大体の柔道家がわからない、それはお前だからできるんだって言われてしまいました(笑)。
伊藤 同じ柔道家でも結構伝わらないんですね。
半谷 目が見えてしまえば、別にそんなことにこだわる必要がないだけで、全盲の人ってくくったらテキストの需要はあると思うんですけどね。でも、あまりにも全盲が少数だから、意見が形にならないんです。
◎相手の体が見えるとき
伊藤 でもサーフィン的な発想も視覚を使ってはいないですよね。どっちかというと、体性感覚系の話ですよね。
半谷 そうですね。つい最近やったばっかりなんでイメージしやすいんですけど、波自体はサポートしてくれる人が教えてくれるんで、ただボードの上が推進力に対して体を整えていく、膝を立てる、足をつけに行く、っていうところの過程は何も見てないですね。
伊藤 やっぱり行けてるなって感じるときはうまくいってるし、うまくいってないときは、そう感じるわけですよね。「乗る」っていう感覚って、もうちょっと解像度をあげてみていくと、柔道の場合は、まず「起こり」で相手を誘導して、重心を崩すわけですよね。 それって、相手だって誘導されまいと思ってるわけじゃないですか。それってある意味で騙すというか、掛け引きっていうかがありますよね。
半谷 そうなんですよね。そこがちゃんと討論できるくらい、私に技術があればいいんですけど(笑)、そこが難しい。
伊藤 でも言語化は難しくても、試合でやってらっしゃるんですよね。
半谷 もともと性格が先に突っ込むタイプなので、先に先に掛けるんですけど、一応自分の中で手順が決まってて。まず、自分の良い姿勢を作る。 釣り手と引き手としてのポジションがいつも決まってて、こっちはここまで上げなきゃいけないと決まっているので、まずそこに持っていくのが第一工程。第二行程で相手をくずしに入るんですけど、第一工程の間に、向こうも自分の好きなポジションに持っていきたいから、やりあいになります。そこの間にぴったり合致しちゃえばそこで一本取れちゃうけど、 攻防が起きて、私がビビったりなんかしてると、なかなか決まらない、みたいなことがある。でもそれが駆け引きの一つになってるかもしれないです。
伊藤 半谷さんにとって一番いいポジションっていうのは、どうやってそこになったんですか?単純に技をかけやすいポジションっていうことですか?
半谷 右手の襟を持つ方が釣り手なんですけど、釣り手はコーチの指導通りに作りました。 コーチの言う理由は、鎖骨のちょっと下なんですけど、ここのポジションに置いておけば、相手が前にパッと出てきた時に勝手に相手が止まるポジションだから、ここでグーを作って立てとけ、と。防御に一番最初に必要な手だから、ということですね。それが低すぎると自分が技をかけたくてもかけられないし、受けられない。高すぎると、掛けやすくはなるけど受け切れない。しかも、私の場合は背が高い方じゃないので、あんまり高い位置を持っちゃうと不利になる。釣り手はそれで決まりました。
引き手は、相手が襟を持っている手をなるべく下げたいので、中途半端に高いと相手の手が自由に動くから、腰まで下げちゃえば相手の手を制せていることになる。制せている時は、完全に自分が「行ける」という状態になります。
伊藤 半谷さんの好き嫌いっていうよりは、相手との関係で合理的に決まってるんですね。
半谷 最初から組んでスタートするんで、いつでも投げられちゃうし、投げれちゃうっていう構図なんです。自分の場合はすぐにはいけない。瞬発的に技は出すことがちょっと苦手なので、まずは自分の安心する形を作らなくちゃいけない。で、安心しないと相手の動きは感じられないから、まずは良い姿勢を作るというのが、勝つための絶対状態。「安心」と「感じる」がセットだからそのポジションを作るっていう感じですね。
伊藤 なるほど。安心しないと感じられないんですね。実際、感じていないときは相手の選手をどういうふうに想像しているんですか?体が全然ない、持っているところしか感じない、ということですか?
半谷 うん、ない。相手がないというか、例えばめちゃくちゃ強くて振り回されるから、ギュッてただしがみついてるパターンの時もあるんですよ。そういうときは、もうその持ってる範囲でしか体がなくて、言ってしまえばただ振り回されてるだけの状態で、相手がないのと同じです。
伊藤 なるほど。逆にこれまでに一番感じた瞬間って、相手がどういう風に見えていましたか?
半谷 手足まで全部ありますね。手と手を握ってるじゃないですか。そこから上半身はだいたい分かる。で、足が右左右左で歩くのも全部見える。で、この息づかいで絶対に体幹が揺れるんですよ。で、その次に軸足が来るから、その軸足を狙って技に入る。
伊藤 なるほど、すごく面白いですね。全然考えたことなかったです。息をすると体幹が揺れて軸足が来る、それは相手が技に入ろうとしているということなので、そこを逆に狙っていく…。
半谷 前のコーチが言ってたんですけど、それが技に入る前のセンディングメッセージだからって。力んでいる選手であればあるほど、そういうセンディングメッセージが出てるんですよね。
伊藤「よーい」みたいな感じですかね。
半谷 そうです。「せーの」って感じですかね。それを私がいつもやってて、こっちが「せーの」っていくタイミングでいつも返されていたんです。なんでだろうって思ってたんですけど。
伊藤 なるほど。じゃあそれが来たら、こちらはうまく返さなきゃいけないということですね。
半谷 パリのときも最後の最後まで難しかったのが、頭の位置です。下を向いてるのか上を向いてるのかがわからなくて、頭まで自分の軌道に乗せてなければ技はかからないって言われたけど、難しいです。今、結局そこは課題で。パリのとき一瞬見えたんですけどね。
伊藤 それって、触っている手の延長で、体の色んなパーツが見えてくるっていう感じなのか、それとも、呼吸とか足音とか、もうちょっと情報が複合的に入ってきて見えるっていう感じなのでしょうか。
半谷 呼吸までわかっているのは試合で研ぎ澄まされているときだけで、普段の練習は手と足と重心の移動とかしか感じられていません。コーチが、相手が次に何したいか、どう動きたいかまで推測できたら勝ちだからって言うので、苦手な動きをまず確認していくんですけど、自分が四方八方にちょっと動かして、反応で相手の体の力み具合を把握します。
伊藤 探るんですね、組んでから
半谷 圧倒的に強い相手だと、探る時間もないんですけど。 探ってると、手と足のばたつきが圧倒的に変わるんで、手足を音も含めて感じますね。
伊藤 手足を感じるというのは、視覚的にイメージしてますか?
半谷 頭の中にイメージを作る作業です。言ってしまえば頭の中で「見てる」。私は夜にイメトレをしたいんですけど、 映像がないから、視覚障害者にはとても難しいなと思ってきたんです。でも相手の体が見えるようになったら、夜のイメトレがはかどるようになっている。そういう分野を誰かが作ってくれたらいいのになと思っています。
伊藤 今日の試合の反省っていうことですか ?
半谷 そうです。 成功体験を頭の中でイメージすることで、本当は1回しかしてないのに8回したみたいな気持ちになるじゃないですか(笑)。繰り返し再生して、次の練習で「こうだったような」と思ってやると再現性が上がってる。これが本当のイメトルじゃないかなと思いましたね。
伊藤 それは音とか重心の変化の感覚とかでは思い出せないんですね?やっぱり映像がないと思い出せないんでしょうか。
半谷 音は確かに一つ有効な手がかりで、実況中継をしてもらった2023年の東京グランプリは、トヨタイムズで実況があったおかげで記憶が長持ちしました。自分の体の記憶と音の記憶が両方合致している状態のものは、記憶が長持ちします。
伊藤 なるほど。ということは言語化も有効なのですね。
半谷 そうですね。私の中で、目印とか思い出すきっかけが全て言葉だから、動きを学んだ時になるべくインパクトワードを残したくて。普段みんなが使わないであろう言葉で表現したい。「黄金の傾き」っていう言い方をしているんですけど、これもみんなは「カカトを使わないで、紙を1枚挟んでやれ」って言うけど、20年分からなかったんです。それがある日突然手に入れられて、 そしたら相手にちょっと乗る感覚になったりとか、自分が1歩前に出てるから自分の前に踏み込みやすい角度になった。 それを思い出すために「黄金の傾きを作るためのアップから始める」みたいな言い方をしています。
伊藤 言葉に感覚を集約させておくのは面白いですね。黄金の傾きを作るためのアップがあるんですね。
半谷 「黄金の傾き」はクロスカントリースキーのダブルポールをやればできちゃうんですよ。ダブルポールで前に飛び出すのが怖くなくなったら、柔道でも前に飛び出せるようになって。
伊藤 面白いですね。なんか本当に奥深いですね。
半谷 いつも似ているものを探して楽しんでます(笑)。
◎「教えてもらっていないもの」がある
半谷 技を学ぶ中で、1個のたとえば「背負い投げ」という技自体は形としてはできている。でも試合の中で使われている実際の背負い投げを、たぶん私は知らないんだと思う。 そこをクリアしないと次に優勝できないから、どうにかしてそっち側の世界を知りたいんです。
伊藤 どう違うんですか?練習と試合では。
半谷 私がやってるのは教科書に載ってるやつで、テレビで見るオリンピック選手がやってるのが、みんなそこを目指してる理想の動き。「阿部一二三の正しい背負い投げを目指せ」とか言われるけど、見たことないからそう言われても困っちゃう。「ここが重要なんだ」っていうときの「ここ」を教えてくれないと、私はそっち側に行けないわけで…。言われたことは全部練習でやってるつもりなのに行けないっていうことは、何か教えてもらってないことがあるはずなんです。早く向こう側が見たいんです。
伊藤 自分が背負い投げをしてもらっても意味ないんですか?
半谷 やってもらって学ぶやり方は、私の場合はレベルが上がってく中で限界が来たんです。技を覚える過程としては、触る、感じる、試して話すっていう工程があって。まず先生にやってもらって形を覚えて、今度は先生にかけてもらって緩急だったり強弱だったり、力の方向を観察して、自分でやってみるという流れで覚えていく。一流選手になってくると、早すぎて訳が分からないんです。 見てても早いけど、受けてもさらに訳分かんない。 分解して練習するんですけど、分解したものを合わせる作業がうまくいってない。しかも分解する作業の練習は私はすごく好きなんですけど、 健常者の多くは分解して練習しちゃいけないって言うんです。でも、それがないと、最初からつなげてやるのは難易度が高すぎてできない。
伊藤 最近だと、バーチャルリアリティ空間で時間の流れをゆっくりにして、卓球のサーブを返す練習をしたりするシステムがあったりしますが、そういうことが視覚なしでできたらいいんですけどね。
半谷 一応部分練習として、相手に協力してもらってやる練習はあるんですけど、結局試合は相手の力が強いので、実際はできないっていうところからまだ抜け出せないんですよね。
伊藤 でもそこにある最後の一ピース、鍵が何なのかっていうのが分かったら すごい気持ちいいでしょうね。
半谷 本当そうで…探し続けているんですけど、難しい。しかも弱視と全盲とでの違いもあって。一緒に合宿したり練習していると、弱視のためにやることは自分には合わないと感じることもあります。でもそれも材料になるはず、無駄なことはなにひとつない、と思ってやるようにはしていますが。
伊藤 残るは金ですね。
半谷 何か、何か脱出する方法が絶対あるって思ってて。「健常者のやり方に近づける方が強くなれるよ」って言われるんですが、私はそれとはちがう可能性を探したいんです。全晴眼とも弱視とも違う、全盲ならではの何かがあると思うんですよね。
伊藤 なるほど。話がもどっちゃうんですが、さっき、先生が「力の通り道」の話をされたっていうお話があったんですけど、力の通り道っていうのは、時間的な話ですか? それとも空間、両方なのかな?
半谷 両方なんですけど、例えば柔道って相手と私の力の向きが一緒になる瞬間があるんですよ。そこが技をかけるタイミングなんです。崩しの中で力の向きがあっちこっち、あっちこっち、いってる中で、力の向きがそろったときに入る。そろったときに入るっていうのが力の通り道なんです。相手の弱い向きを探していって、 こっちに弱いなら一回こっちに振ってから技をかけに行く、っていうのが崩しですね。
伊藤 一回反対側にそろえて逆に振るってことですね。
半谷 これがセオリーみたいで、背負い投げをしたいなら一回押してから入る。大外刈りをしたいなら引いてから入る。
伊藤 想像していたのと全然違う意味でした。力が通りやすいところがあって、そこに流していく水路みたいなイメージを持ってました。
半谷 スキーのほうが水路っぽいかもしれないですね。
伊藤 逆に、相手から力の通り道に誘われちゃダメなわけですよね?
半谷 あ、そうです。 誘われるときは一瞬ですけどね。抵抗しようがないんですよ。うまい人になればなるほど一瞬です。自分の姿勢を崩された段階でもう戻せないです。健常の人たちって組み手争いがあるじゃないですか。彼らは持たれた手を引きちぎる動作が卓越してるので、例えば健常のコーチたちと組んでからスタートしても、すぐ釣り手と引き手を引きちぎられちゃって、私が両手を持たないまま引きずり回されたりとかするんです。その中で相手の動きを探しに行くってなるとすごい難しいけど、そういうきつい練習の先にもちろん得るものがあるのでやっています。弱視の選手は、相手の襟が見えていて、頭の位置を固定できるからいいけど、私は頭をシェイクされちゃうんで、気持ち悪いと思いながら練習してます。
伊藤 頭の位置にまで影響が出るんですね。気持ち悪くなっちゃうんですか。
半谷 見えなくなってからは、自分が頭を振る回転系の加速度の左側に弱いのと、自分の意図とは関係ない方向に振り回された時に、めまいが出るようになってしまって。スキーのくだりも左に回る時にちょっと注意しないとくらってきちゃって。
伊藤 なるほど。難しいですね。相手に、こちらの動きを感じさせない技っていうのはないんでしょうか。例えば、上半身は相手の手が直接触れてるから、下半身はそれとは違う向きを向いている、とか。こちらからむしろ騙していく、というような、そういうやりとりもありえますか。
半谷 日本人は右組みで持ったら右足が前っていうのがセオリーなんですけど、海外の選手は関係ないんで、右組みでも左足が前に出たりとかする。教える段階で多分違う教え方をしてるんだと思います。私は、かけ損じることがかなり多くて、「足ないじゃん」ってなるときがあります。私がやる騙しみたいなのは、右足をすごくアピールしてついてるように音で出すんですけど、実際は左足に80%ぐらい体重が乗ってて、右足を刈られたところで何の問題もなくて、それをさらに刈りに行くっていうことは、やっていますね。
伊藤 そのあたりはゴールボールとかにも近そうですね。音でちょっと騙す感じですね。
半谷 「トントン」と「ドンドン」の振動の違いという感じですね。
伊藤 それは晴眼の柔道にはないやりとりですよね。
半谷 いやでも晴眼の方がやっぱ卓越していますね…。足を振って行くぞ、行くぞって見せかけて違う技に行くっていうのをよくやってて、それは目線でも行われてるってこの前聞いて。目の向きで 相手にフェイント出してる。で、今オリンピックで 金メダル取った田知本遥さんがコーチに入ってくれてるんですけど、私とやりながら「半谷さんにフェイントかけても無駄だった」って言ってました(笑)。それは新鮮だったけど、でも他のスポーツと違って柔道だと目隠ししても健常の人の方が強いんですよね。見えなくても体性感覚を研ぎ図ませてできちゃう。
伊藤 そうなんですね。
半谷 やっぱり体に染み付いたことだから、学ぶ過程に問題がなければ、目隠ししてもできちゃうんですよね。
だからこそ、指導の時に歪みが起きるんです。目をつぶってもできるぞ、こんなの子供でもできるぞって。この2ワードがきついんですよね(笑)。いや、分かった分かった、じゃ教えてって思うんですけどね。いまは新体制になったばっかりなので、その共通言語の作成から始めなきゃいけない。それが毎回大変なので、さっきの話に戻りますけど、テキスト作りたいなって思っています。自分はパラリンピックに4回出てるんですけど、そのたびに体制が変わっているんです。
◎テキストの構想
伊藤 半谷さんが考えているテキストっていうのはコーチと共有するものなんですか?
半谷 もともとは、育成とか普及とかの意味で、始めたばかりの子のために作りたいって思ってきたんですけど、自分が競技する土台も固まってないのに、それじゃだめだなって思いました。というか、自分が勝ちたい気持ちが多分どんどん強くなってきて、むしろ私に必要じゃんってなってます。
伊藤 でも、それが一番いいものになりそうですけどね。 具体的なイメージはもうあったりするんですか?
半谷 そうですね、一応、分け方としては、「触り方」と「聞き方」と「イメージの作り方」の三部構成を考えています。「触り方」は「触り方」「触らせ方」っていうふうに分かれて、「聞き方」は「質問のテクニック」っていうことで、視覚障害者って、経験値によってイメージの幅が違うから、質問の幅も変えなきゃダメだよね、 みたいなのを盛り込み、「イメトレ」に関しては、自分がパリに向けて初めて着手したんですけど、 見えないけどイメトレってどういうことをやっていくの?っていうところを考えています。でも勉強はあまりしてこなかったんで、やばいです(笑)。
伊藤 なるほど、面白いですね。『体はゆく』っていう本に書いたのですが、何かを伝える、教える、というときに、スポーツのような体の動きの場合には、体の形や動きを外から直接教える場合と、たとえば「紙風船をやさしくつかむ」のように、何らかの道具や目標となるポイントを設定し、そこに向けて体を動かしていくと自然と形ができあがるという場合の二通りがあるように思います。
半谷 記録で争う種目の選手は、自分の体に他者が触れないからその二通りで成り立つけど、柔道の場合は他者が触れながらやるから、両方を持っておかないと強くなれないんじゃないかなって、今聞いてて思いました。自分は自分に意識を向ける作業と、外から見る作業は両方別でトレーニングしていて、そのためにルービックキューブを始めたんです。自分が試合場のどこに立っているか、とか、さっきを受けた技を自分に置き換えたらどうなるかっていうのを、上から見る作業をしているんです。ルービックキューブも外側からじゃなくて内側から見るように意識をしていて。外側から見ることが、技を作っていく過程で必要かなって思うし、同時に、自分の真っ直ぐ、左右前方、上下の真っ直ぐが整っている状態じゃないと 相手を感じることができないから、自分に意識を向ける作業が必要です。外側から見る作業と自分に意識を向ける作業、両方を同時にしていないと、試合の中では、相手の動きを感じ、自分の動き方が正しいか感じる、 両方が見られなさそうだなと思いました。
伊藤 すみません、ルービックキューブを内側から見るっていうのは、どういうことですか?
半谷 なんでそうやって表現するかって言うと、見てるときは外側を見てるじゃないですか。でも触った段階で、もう体の内側になっちゃってるイメージなんです。『目の見えない人は世界をどう見ているのか』の中に、壺の中に絵を描いている人の話があったと思うんですけど、それと似てるなと思っていて。触ったものが外か内側っていう作業をどこで作るかっていうと、私の中ではそれが内側になるんですよ。
伊藤 ルービックキューブの中に自分が入ってるってこと?
半谷 そう、そんな感じ。
伊藤 じゃあ「天井黄色だな」みたいな把握の仕方ということですか?
半谷 コマの向きを必ずイメージしながら 回していくんですけど、外側から見ていると ただ外を触ってるだけなんだけど、触って動かすことによって、内側なんだけど…なんでそこだが内側になるんだろう…一回、手を介すことによって内側になるんですよ。見えてる人は、触る手は目の役割をしていないけど、私の手は見る役割をしているから、外側から見ているわけじゃなくて、自分の体に入っている感じ。 一回、目を使わずに頭の中でイメージを作るから、「中」なのかな…
伊藤 頭の中にルービックキューブが出来上がるってことですね。
半谷 そうです。目で見たものは外からだけど、私は頭の中でもう一回作るから。
伊藤 なるほど。つまり、そうやって頭の中に作ったルービックキューブと、客観的にルービックキューブを見ることは違うんですね。
半谷 あ、違う。絶対違う。例えば、試合場を見るときに、見えている人の言葉を聞いたら間違うんですよ、絶対。一回自分の中でイメージを自分なりに作らないと、指示通りに行ったら間違う。
伊藤 例えばどんな指示が間違いますか?方角に関する指示とか、距離に関する指示とか…。
半谷 そう、試合中に「下がってるよ」と言われて、どっちに下がってるのかを、審判の声と自分のコーチの声と自分が実際立ってる位置の3点を一度作って、どっちに動くかを判断する。
あとは、練習中に理解する場合。相手と自分がいて、技をかけたら相手は下がるから、その反動を使って技をかけるんだよ、ということを説明してもらうじゃないですか。そしたら、それを外側から見る作業をするんです。説明してもらうときは相手と組み合った状態で、「じゃあやってみて」っていう自分が体験した状態で教えてもらうことが多いんです。でも、自分の体験だけじゃ印が1個もなくてブレブレの状態だから、外側に視点をつくって、相手が斜め前に向かってきてるのに対して、私がこう入るんだよね、っていうことを外側から見ないと分からないんです。見た経験があるから、頭の中で映像を作りたいという欲望なのかもしれないですけど。
伊藤 なるほど。ルービックキューブをやることで、そういう、頭の中で客観的な映像作る作業の訓練になるっていうことですね。
半谷 そうです。たとえばルービックキューブの白いブロックが2回転させたときにはどこにいるかを想像することと、柔道で1歩出した後に次の足がどこに向かっているのかを想像することが似てるなと思います。
ルービックキューブのブロックの動きを一度に何点まで追えるかっていう作業を自分はするんです。柔道だと後ろ向きになって手をさばくこともあるんですけど、頭の中で裏返しにしなきゃいけないから、そういう点対象をイメージする練習になります。
伊藤 すごく面白いです。 そんなに俯瞰視点が重要だと思っていませんでした。体が触れ合ったところから相手の体の全体を理解するようなことかと思っていました。
半谷 まだ熟練度が足りないのかもしれないですけどね。 考えすぎなんですかね。でも努力の土台に立つまでの努力が必要なんですよね。
伊藤 そっか…。でも先天的に全盲の方の場合は、俯瞰的な視点がおそらくなかったりしますよね。どうやって対戦しているんですかね。俯瞰視点がないとできないのかな。
半谷 先天的に見えていない選手だと、やっぱり技の習熟度に差が出てしまうので、そこをカバーできる何かを見つけられたらいいなと思うんですが…。私はそこにこだわりすぎて、練習しないでストライキみたいになります(笑)。
伊藤 そうですよね、納得していないのに練習しても意味ないと思っちゃいますよね。
半谷 「力を抜いて」ってよくみんな言うじゃないですか。でも力を入れている理由がちゃんとあって、どこから何が飛んでくるかわかんないから肩の力が抜けなかったり、特に柔道なんか早い強い選手はどこから技がくるかわかんないから力を入れてる。そういうすれ違いがあって、色々考えたんですけど、やっぱ抜いちゃいけないなって思ったんですよね。力を抜くことが多分全てのスポーツに共通する事項で、それと同じくらい視覚障害者が上達する事項が必ずあるから、将来的には視覚障害者の基礎練習になるような練習を作ってもらえたら、各組織でトラブルが起きなくて済むんじゃないかなっていう願いがあります。
伊藤 そうですよね。なにか共通していそうですよね。探したいですね。
半谷 質問したいことがあるんですけど。
伊藤 はい。
半谷 いろんな視覚障害の人に話を聞いていると思うんですけど 共通点みたいなのってあったりするんですか?客観的な出来事と感情的な出来事と、育ってきた背景と、いろいろなことでズレが生じて、そこからトラブルが起きやすいんですけど、共通していることはいったいあるのかなっていう疑問があって。
伊藤 なるほど。共通してること…。柔道の練習場では、弱視の選手も全盲の選手も一緒に練習してるんですか?
半谷 ふだんは全然バラバラに練習してて、わたしは健常の中学生に練習してもらうことが多いんです。でも強化合宿のときだけ弱視の子と、あと私のほかにもう一人、 全盲の子がいて、一緒に練習をしています。
伊藤 柔道と関係ない生活の場面でも、他の視覚障害者とはあんまり関わりはないですか?
半谷 そうですね、ブラインドサッカーとかに行けば会いますけど、日常生活の中ではいないです。
伊藤 なるほど、そうですね。確かに、共通してることって言われると、答えに困りますね。みんなものすごく違いますしね。
見え方が違っても同じ視覚障害者で仲間だと言う人もいれば、盲学校の頃からトラブルをいっぱい経験して、あまり一緒にいたくない人もそれなりにいるなと思いますよね。さらに、そういう人が、自分も障害者なのに障害者に対してすごく差別意識を持っているのではないか、と考えて苦しくなる、という話も聞きますね。
半谷 いろんな競技団体に所属してみて、場所によって全然違うなと感じます。たとえばスキーに行くと、私は全盲でお手伝いは何もできないけれど、責められることはほとんどなくて、逆に弱視で0.1ある女の子の方がもっとできるでしょうって言われちゃう。でも柔道に行くと、全盲は手がかかるからって言われて、うわってなるときはまあまああるんです。逆にブラインドサッカーに行けば、見えなくて介助が当たり前だから、それは苦にならないって聞きます。
伊藤 面白いですね。それは、その種目の特性なのか、そのコミュニティの特性なのか、どっちなんですかね。
半谷 競技特性は多くあって、柔道は個人競技で、実力主義、強い者は強い。私は成績を残したおかげで、そんなに虐げられないんだと思います。ブラインドサッカーは団体競技なんで、だいたい目をくばってくれる。スキーは、他の障害の方がいらっしゃるんで、 私1人が目が見えなくても、まわりは手足がなかったりしても目は見えるんで、それで補いあってくれる。私がただ座っていたとしても、できることをやればいい、 ちょっと寛容な感じではあるんですね。隣にいる弱視さんたちとの関係性が、場所によってすごく変わるので、「何が起きたんだろう」って毎回不思議に思うんです。
伊藤 弱視の人と全盲の人の間の溝が、外側から作られちゃう、ということなのかな?
半谷 外側から作られた結果、仲良い友達と話していても、私が全盲の代表として、友達が弱視の代表として話さなくちゃいけないことがあって。「仲良いのに、なんで代表したら喧嘩しなきゃいけないの?」っていうやりとりをしてしまうと、不毛だな、まわりが求めるからこんなやりとりをしてるんだって思っちゃう。
伊藤 なるほどね。代表として扱わないでほしい、という言葉は、他の障害に比べて視覚障害の場合にはすごく頻繁に聞く気がします。
半谷 全盲の方が大変だけど、弱視の方が助けてって言いにくいんだよっていう理屈は理解できるんです。釣り合いを取ってって言われた時に、全盲は全体を把握できないんです。 弱視さんが声をあげてくれない限りは、配慮は難しいわけなんですよ。「半谷さん、いつも欲張りなんだから」って言われるけど、状況が分からないと加減も読めない(笑)。みんな、手が掛からなくて楽な選手、期待されてる選手って思われたいっていうのは人間の心理なので、しょうがないかもしれないけれど、何も言わないことで秩序が保たれる状態というのは、スポーツの業界としてどうなのかな、と思ってしまうこともあります。必要な情報が欲しいから、話したいだけなんですけどね。そのためにもテキストがあるといいなと思います。
伊藤 そうか、そのためのテキストでもあるんですね。
半谷 最終的には自分の身を守るためなんです(笑)
伊藤 いや、でもそれは絶対後輩にとっても助けになるものですよ。たくさんの選手と現場を救うと思います。
2025/9/8 @後楽園のカフェにて