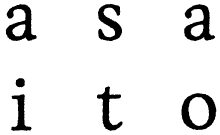ムーンさんは希少疾患のため、顔が黒くなるという症状を持っています。ところが、顔が黒いせいで、子供の頃から「むしろ日に焼けて健康的」と見られがちだった。そう見られることで頑張れた部分もあるけれど、ずっと「女優」が抜けないといいます。たしかに、ハキハキしゃべるムーンさんにはエネルギーにあふれているようにも見え、インタビューしていても引き込まれそうになります。体じたいの生理的な大変さと社会的な見え方のギャップのあいでで生きる可能性と困難について語ってくださりました。
ムーンさんプロフィール
生まれつき希少疾患があり、1日3回の服薬と3か月に1度の通院が欠かせない。障害者手帳なし、指定難病あり。趣味は、小説を読むこと。
◎大人たちの見解
ムーン 私はこの、顔が黒くなる、ACTH不応症と言われてきたんですけど、先月、実際は病気が違うって言われて。
伊藤 なんと、先月。そうですか。
ムーン 簡単に言いますと、太陽を浴びると肌をやけどする病気の人がいますよね。それの、やけどはしないんですけど、ヘムっていう物質がかかわるポルフィリン症っていう病気があるんです。ポルフィリン症は原因によって8つか9つの型に分類されるんですけど、そのうち患者数が少ない、1つに類似する病気 だっていうのが、分かりまして…。
伊藤 それは、ずっと同じ病院にかかって、このタイミングで分かった、ということなんですか?
ムーン そうですね、 はい。それもお話したいことの一つでもあるんですけど、やっぱり生まれつき病気なので、「自分の症状」と「意思決定する大人や医師の見解」っていうのが合致しないときが結構あって。この顔の黒さを改善しなければ生きていけないので、これを改善する治療法の1つがACTH不応症じゃないかっていうのは、ずっと言われてきたんです。なので、これを治療することによって生存はできたんですけど、主症状というのは全然改善されないできていて…
伊藤 主症状っていうのは何ですか?
ムーン お腹が痛くなるんです。これが改善されなくて、過敏性腸症候群じゃないかとか、気の持ちようじゃないかって、特に思春期は言われて。結局、遺伝子検査をして病気が分かったんですよね。
伊藤 そういうことは、お医者さんはどういうテンションで伝えるんですか? これまでのいろんな治療のプロセスが、間違っていたわけじゃないかもしれないけど、思っていたのと病名が違っていた、これからだいぶ扱いが変わりますよっていう話ですよね。それをご本人にどんな伝え方をするんですか?
ムーン 納得いかないです、とは言いたいなと思っていて(笑)。なんかやっぱり、私の病気っていうのは若干モルモット化してるんですよ、少なすぎて。
伊藤 なるほど。
ムーン 私という人生が生活としては保障されてないんですけれども、医者としての好奇心対象としては大切に扱ってはくれるんです。医学の発見としては大切にされてるんで、なんか病名についても「分かったよ!」みたいな感じで言ってくるんです。
伊藤 あ、そっちなんですね。
ムーン かといって何かが変わるわけではないみたいなテンション感で…。
伊藤 そっか、生まれつきの病気だと、気づいたら周りに大人が取り囲んでいて、専門家がいて、彼らの方がいろんな言葉が使えたりとか、解釈ができたりするから、実際に病気を経験している本人が後ろに行きがちというか、後回しにされがちなんですかね。
ムーン やっぱり医学って絶対的な権威という感じがあって、医師の診断書の効力が強いじゃないですか。そういう中で腹痛とか、神経症状とか、脱力とかも結構あったんですけれども、最初に診断された病気の症状にないので、そもそもの働きかけが悪いんじゃないかとか、生き方が悪いんじゃないかっていうふうに、パーソナルな理由のせいにされたり、いっぱい食べないのが悪いんじゃないかって言われて、すごいいっぱい食べさせられて、お腹を壊すとか…。かといって、正露丸とか腹痛の薬を飲もうとすると、気持ちが弱いからだって言われて薬を捨てられるとか…。親も悪い人ではないんですけど、昭和の人間なので、メンタルの方にいってしまう(笑)。
伊藤 気合いとか気の持ちようとか…(笑)
ムーン いや、医者に行っても「正しい」って言ってるんだから、子供であなたの意見が違うんだよ、って。私もセカンドオオピニオンとかいっても、未成年だと、大人の力が強くて…。
伊藤 なるほど…。
ムーン お医者さんとは正直、良好なコミュニケーションを取っていたと思っていたんです。けれど、よくよく大人になって振り返ると、まわりを知らなかったからよく思ってただけなんだなーっていうことに気づいて。いろんなジャッジができるようになったときに、振り返ると結構ひどかったなと思うようになりました。
伊藤 病院は、毎月通院するような感じだったんですか?
ムーン そうですね。小さい時は月1回です。大人になって、症状がすごく変化するっていうことはないので、薬をもらうために、処方箋の期限である3カ月の範囲内に行くっていう感じでした。でも ストレスを感じると、腹痛とかいろんな神経症状が出てきて。年齢を重ねるとやっぱり社会的にもいろいろ負荷がかかってくるじゃないですか。そうすると、いろんな症状が出始めたんです。
伊藤 現状、一番症状としてしんどいのは腹痛ですか?どんなときになりますか?
ムーン 食べたあととか、あとはもう日常茶飯事です。毎日痛くて、芋虫を飼ってるような感じです。動いてる。
伊藤 それはトイレに行けば済むという話ではないんですか?
ムーン 済むんですけど、またその同じ環境に行けばおなかが痛くなって、それが改善するまで布団の中とかで横になっているという感じですね。
伊藤 ストレスの原因は対人的なものですか?それとも光など刺激ですか?
ムーン そうなんですよね…。光が悪いっていうのは最近知ったので、正直その因果関係の特定はできてないということがありました。 確かに昔からあんまり外でやる体育とか、得意じゃなくて。水泳とか室内だったら大丈夫なんですけど。なんで、若干関係あるかなと思っています。一番はやっぱり、しゃべるとかは得意なんですけど、テストのときですね。
伊藤 テストで緊張して痛くなるっていうことですか?
ムーン テストでいい点をとらなきゃっていうストレスですね。
伊藤 以前、テレビの記者をされていたとメールで伺いましたが、人前で話すのは大丈夫なんですね。
ムーン そういう瞬間芸だったら大丈夫なんですけど(笑)、テストって20分とか80分とか戦うじゃないですか。それに脳とか体がついていかないんです。
伊藤 テストが始まる前から痛いんですか?
ムーン 1週間ぐらい前から、熱出しちゃってました。それがあらかじめわかったので、別室受験をしたいっていう相談もしたんですけど、障害者手帳があるかないかっていうのが、当時は、ポイントだったんです。
伊藤 診断書じゃないんですね。
ムーン 最終的には診断書でもよかったんですけど、診断書でいいっていう話になるまでに結構時間がかかりました。
伊藤 じゃあ中学生になるともう定期テストあるし、受験もあるし、その都度熱出しちゃう感じだったんですね。
ムーン そうです。
◎顔の黒さが挑戦を支えてもいる
伊藤 現職ではその病気のことは話していないんですか?
ムーン 今の職場では話していて、かなり配慮をもらっています。
伊藤 どんな配慮をもらっているんですか?
ムーン テレワークです。これが結構大きくて。肉体は動かないんですけど、頭は動くんです。私の頭をパソコン上でも再現してくれるので、テレワークはありがたいです。
伊藤 なるほど。一日、どんなふうに過ごされているのか知りたいんですけど、事前にいただいた情報だと、お薬をかなり飲まなきゃいけないというのがありますよね。ご自宅でテレワークするってなったら、朝食食べてお薬飲んで、仕事をして、昼食食べて…
ムーン 昼食食べてお昼休みギリギリまで寝ていますね。
伊藤 そうすると腹痛もないんですか?
ムーン 家にいる分には腹痛は全くないんですよね。
伊藤 そうなんだ。
ムーン 会社に行くと起こるんです。会社にいるときは頻繁にトイレにいきます(笑)
伊藤 なるほど…。でも基本的な性格としてはムーンさんは外向きなのかなと思うのですが…。お話しをするのが好きだったり、挑戦する気持ちがあったりとか。でも、体がちょっと家にいたいっていう感じなんですね。
ムーン その挑戦するものを支えているのが、顔の黒さなんです。「日本人」ってひとくくりにするのもおかしいかもしれないけれど、日本だと「顔が黒い=元気、パッションがある人、健康的な人」っていう解釈をしてくれるんですよね。 なので、私は、具合が悪くて顔が黒くなってるんですけれども、すっごい元気だねって言われるんですよ(笑)。就職活動でも、顔が黒いからアグレッシブに見られるんです。 もちろん、今まで自分が頑張ってきたところもあったとは思うんですけどね。なので、私の顔の黒さは、自分としては具合が悪いんですけども、なんかポジティブさを表す表現にもなっちゃってて。
伊藤 なるほど…。間違ってるけど間違ってない、みたいな感じですね(笑)。
ムーン 顔が黒くなる病気の人は、世の中にいるとは思うんですよね。でも、そういう人がいるっていうのが、まず知られていない。それに、私というキャラクターと顔が黒くなるっていうのが合わさってる。それが私を支えてきたものでもあるんです。
伊藤 逆にね…興味深いですね。
ムーン 初対面では元気と見られても、長い時間を過ごすと私の体力が分かってきますよね。体を動かすことによって得る言葉っていうのがあると思うんですけど、そういうのが分からない。変わった子と見られて、距離を置かれやすかったですね。
伊藤 周囲とのギャップを感じたエピソードはありますか?
ムーン 最近、障害者雇用で働いている人と関わることがありました。手帳を持ってる人です。その時に、ある疑問を投げかけられたんですよ。
伊藤 なんですか?
ムーン 「なんでムーンさん、そんなに頑張ってるの?」って。 理由としては、障害者の人って、公的なお金をもらえたり、社会的サポートもあるので、言葉は悪いんですけど、仕事でそこまで成果ださなくても生きる手段があるらしいんです。私もそういう人だと思われていたらしくて、それで一生懸命仕事をして、結果を出そうとしているのが、なんか変わって見える、卑しく見える、って言われちゃって。
伊藤 卑しく?どういうことですか?
ムーン 上に上がろうとしてる、健常者と張り合おうとしている、っていうことだと思います。病気があるとか、障害があるというときに、それを隠してではないんですけども、伏せてまで、頑張ってる感じがするみたいで。その人だけじゃなくて結構言われやすいんです。やっぱり健常者の人についてきて、そう思ってきたのかなと思います。
伊藤 なるほど…ムーンさん自身は、自分が頑張りすぎなぐらい頑張ってるっていう感覚あるんですか?
ムーン あります。逆に演じてるかもしれない。 やっぱり女優ですね。病人として本当は生きたいけれども、障害者手帳という公的な支援がないし、サポートもないから、健常者として見られるように女優となって演じていて。私が言葉にすることって、すごく健常者理想的な感じなんですよね。ドラマで見た「こういう大人が素敵」みたいなものがすごく投影されていて、自分がないんですよね。
伊藤 生きる道を自分で見つけるために演じなきゃっていう感じですか?
ムーン その瞬間をしのぐために演じていたという感じです。当面の見通しは持っていなくて。最近は道筋があるんですけどね。その場をしのぐために誇張して演じるっていうのが、自然になりすぎて、自分が分からなくなってるっていう感じでした。
伊藤 演じてるっていうのは、演じるのをやめて、自分の素の状態に向き合うのが怖いっていう感じですか。
ムーン 素の状態が分からないっていう感じですね。障害者の人たちは、多分なんですけど、障害があって、学校とかの生活のなかで、自分が障害者だという感覚がわかっていくんだと思うんですよ。私の場合は病気なんですけども、障害者手帳がなく、さらに普通の人って言われる人たちと同じ体育をして、同じ時間割り通り過ごすことを良しとされていて、でもついていけないんですよ。ついていけないから、下を向きながら涙を流しながら、前を見て笑うみたいな生活をすごしてきたんですよね。
伊藤 なるほど。小学校くらいからそういう生活をしてきたということですね?
ムーン 記憶にあるのは4歳ぐらいのときですね。これは結構よく覚えてるんですけども、病院に行くので、月一回、幼稚園を遅れていく時があるんです。 で、遅れてきた人は、みんなが外遊びしてる間に職員室みたいなところで、お菓子食べながら待ってる、みたいな時間があったんです。 で、そういう子が他にも何人かいたんですよ。私もお菓子を食べながら、やっぱり体がだるいので、このままずっと待っていればいいのになぁって思ってたんです。でも、10分ぐらい休憩してる間に、「じゃあ、ムーンさんも一緒にやりましょう。」って言われて、嫌いな遊びに参加させられたんですよね。 そのときに「そっか、このままお菓子食べていると病気の私は受け入れられないから、これから元気な子を演じに行くんだ、健常者という世界に飛び込んでいくんだ」、っていう感じがあったんです。
中学校の時もそうで、近所の仲がいい子に、「明日は病院に行くから遅れるね」って言ったときに「体も悪くないのに病院に行って休むって仮病じゃない?」 みたいなことを言われて。
伊藤 そっか…切ないなあ…お菓子食べてる時の体のだるさは覚えてますかね?
ムーン 直立できないほどの身体の怠さがありました。でも、外遊びして楽しくやりなさいということになると、なんかのアドレナリンが出てできちゃうんですよ。それが結構私の矛盾するところで。
伊藤 でも家帰ったらもうぐったりじゃないですか?
ムーン はい。親はそういう姿を見てるので、「この子は社会でやっていけるのか」というと思いもすごく強くて。
伊藤 その頃は、病院に行くときは、お母様が一緒に行っていたんですか?
ムーン そうです。
伊藤 お母様とお医者さんが話すみたいな感じですか?
ムーン これが結構やっかいで、親もやっぱり心配はしているんですよ。親から見れば、「薬を飲めば普通の人」っていう見方が強かったんです。親と私ではキャラクターが違っていて、内向きな感じなんですね。それで、親としては、子供の病気を外にまで行って理解してもらうんだったら、あなたが我慢しなさいっていう感じになったんで。
伊藤 薬との付き合い方に苦労している方は多いですね。 「薬を飲んだら普通の人」っていうのが希望なんだけど、それがうまくいかないと、なんか自己責任みたいになっちゃう。自分の体の状態を素直に出してはいけない、と感じたのはいつごろですか?
ムーン 社会的に感じたのは小学校3年生のときです。5限目ぐらいの授業で具合が悪くなったんです。けっこう騒がしいクラスだったんですけど、「具合が悪いから保険室に行ってきていいですか」って聞いたらOKされたんです。でも放課後に誰かの家に集まって遊ぶことになったときに、具合がよくなったから参加したんですね。 そしたら、後日「5限休んだのは仮病だったんじゃないか」って言われて。薬飲んだりしたんで復活したと思うんですけど、「ちょっと休んで体調が戻る」っていうことに対して、周りが冷ややかだったんですね。一定に保っていかなきゃいけない、波を表現しちゃいけないというプレッシャーがありましたね。
伊藤 そうか、波が大きいんですね。寝たら治るとか、薬飲んだら治るとか…
ムーン あとご飯を食べて調子悪くなったりするので、みんなにとってエネルギーになることがエネルギーにならなかったりする。そういうのも大きいかもしれません。
伊藤 肌の色も変化するんですか?
ムーン 私はやっぱり自分のことなのでよくわからないんですけど、変化しているみたいですね。プレッシャーがかかるときの小学校の写真とか見ると、すっごい黒光りしてて(笑)。 でも本当になんか「ピカっ」ていう感じなんです。やっぱり他の人たちは日本人なので、あまり特徴がないのもあって…
伊藤 それは頑張ろうとしてるから光ってるっていうことですよね?
ムーン その通りです。それで、さっき言ったように元気になれる。「ムーンいいぞ!」みたいになる。
伊藤 メカニズムとしては、黒くなる物質が作られちゃうっていうことですか?
ムーン ヘムを作る力が弱くて、私は70%とか60%しか作れないので。ヘムが作れない理由は、作るのに必要な酵素のどれかが欠けているかによって症状が違っていて、私はおなかが痛くなったりする症状でした。
伊藤 しびれとかもあったりするんですか?
ムーン 脱力がありますね。力が抜けてフラッとなります。日常生活で倒れたらあぶないので、気を高く持ちますね。倒れるまではならないんですよね。100%は動いてないけれど、全く作用していないわけでもない、という感じです。
◎点としては存在しているんだけど、直線ではない
伊藤 家系で同じ病気の人はいたりしますか?
ムーン 親も兄弟も問題なくて私だけなんです。これから結婚とかしたいなと思うけど、どう説明していこうか、どう理解してもらおうかと考えてしまいます。相手も、やっぱり1人の人間であるし、社会の1人でもあるじゃないですか。その人を通し、社会としても、受け入れてもらったときに、初めて分かってもらえたと感じるのかなと思います。
伊藤 社会として受け入れられるっていうのは、なんか制度的なことじゃなくても、対人的なところですか?
ムーン 働いていて思うんですけど、人って、私も見てるけども、私をどう社会が受け入れてるかみたいなのも見てるんですよね。今は多様性の時代じゃないですか。10年前ぐらいに自分が主張しても誰も聞いてくれなかったんですけど、最近は普通の人も聞いてくれるようになりましたね。
伊藤 同じ病気の方ともお会いしたことはありますか?
ムーン 大学院でこの病気について研究したときに、この病気を包括するのがアジソン病っていう病気なんですが、その人には何人かお会いしました。
伊藤 その時どうでしたか?仲間感はありましたか?
ムーン ありましたね。ただ私みたいに積極的に動いている人がいるわけではないので、そこに関して噛み合うかというとそうでもなかったですね。
伊藤 そうですね…。当事者会にいくと仲間がいてほっとするという人も多いのですが、逆にその中で優劣を争うような雰囲気に違和感を感じたり、自分の悩みが病気や障害に集約されることに納得できなかったり、付き合い方が難しいという声も聞きます。
ムーン それはありますね。私が行ったところはもっと上の世代の人が多くて、諦め感がありました。理由としては、私たちが働けなかったんだから、あなたにも諦めたほうがいいっていう感じなんです。しかもやっぱり嫉妬もあると思うんですけどね。相談の対象にはならなかったです。それは切なかったですね。
伊藤 先輩として、 若い人も自分と同じような人生を歩むべきだ、そうじゃないと自分が否定されちゃう、っていうのがあるんでしょうね。意外と、違う病気の人と話したほうが話が合うっていうケースもありますね。人に理解してもらうときって、ちょっと抽象化する必要があるじゃないですか。その抽象化をするときに、別の病気と自分の病気の共通点を探すという視点で話していくと、分かりやすくなる。
ムーン 今、それをすごい自分の中でも大切にしていて。どうやったらそれをうまい具合にできるかなと思っています。探している感じです。私を取り囲んできた大人は、もう深いというか、客観的には見られない領域にいるんですよね。違う世界観にしてもらいたいですね。
伊藤 そうですね。今回も谷田朋美さんについての私の原稿を読んで連絡をくださいましたが、彼女も科学がちゃんと自分の体を説明してくれないときに、自分でどうにか体の居場所を作っている方なんですよね。
ムーン そうですね。変わるといいなと思っているのは、ずっと病気だということを言わない生活をしてきて、25歳くらいで病気だということを言って生活するようになったら、やっぱり否定的な部分が出てきちゃうんですね。病気の人はこういうことができて、こういうことができない、というのが勝手に決められちゃうというのが最初のプレッシャーとしてあって。私はそれを否定できるパワーもあると思うので、流れとしては否定できるんですけども、最初のプレッシャーとしては、「そこですか?」みたいな感じで噛み合わない状態で始まるんです。人よりワンクッション工程が多い。
伊藤 障害の世界でも、パッと見て分かる障害とパッと見て分からない障害というのがときどき話題にあがります。見て分かる障害は、車椅子ユーザーのように、最初に先入観が強くて、徐々にそれを埋めていく形になる。一方、見てわからない障害は、だんだんズレが開いていく形になりやすい。ムーンさんはどうですか?
ムーン 言った瞬間にも広がるし、言わなくてもやっぱり体力的には違いがあるので、演じきれなくなったときに崩壊が起こる感じです(笑)。で、崩壊からの切り替え方は、そのコミュニティから離脱するという形になります。なので、親からは、何でも熱しやすく、冷めやすいって言われるんですけど、別に私は熱しやすくて冷めやすい性格じゃないと思っていて。ついていけないんです。そこを補ってくれる、下駄を履けるようなものが、今は配慮としてあるんですけど、ずっとなくて、ついていくしかなかったです。
伊藤 なるほど…。そのついていけない感じについて、もう少しうかがいたいです。体育の授業が体力的についていけないというのはイメージしやすいのですが、たとえば今の職場とかでもついていけないという感じはありますか。
ムーン やっぱり人生としてついていけないですね。高校卒業からいろいろあったんですけど、誰もそんな経験しないじゃないですか。見た目は普通なので、30歳女性はこうしている、というのがあると思うんです。結婚してるとか、その兆候がある、みたいな。 どこか、やっぱ求められるし、発言として期待されるんですよね。 そこにハマっていないときに、私は演じきるわけですよ。それで評価される。虚しい。
伊藤 なるほど…
ムーン 自己肯定感を上げたいわけじゃないんですけど。なんかつながってほしいんですよね。今は点としては存在しているんだけど、直線ではないんですよね。
伊藤 さっきおっしゃっていた、うまくいかなくなるとコミュニティを離脱してきたっていうふうにおっしゃっていたけれど、結構そのスイッチが多いっていうか、ずっとつながっているものがないっていう感じなんですかね。
ムーン つながっているのは「生きてる」っていうことだけですね(笑)。その中でもどうやったらいいのかなって。
伊藤 完全に独自の道を行く人もいるじゃないですか。世の中の主流派とは全然違う、独自の生き方でそれを肯定していく人。それはそれですごい面白いけど、でも現実問題、そうじゃない人の方が多数ですよね。隠せたり演じられるという選択肢を持っている場合は、特にそっちに行きがちになりますよね。でも、そのやり方の振り切れなさみたいな、主流派に乗っかったり落ちたりするっていうところは見えなくなりがちですね。つながりも生まれにくいし。
ムーン 周りもそうだけど、自分としての自己認識もけっこうあったなと思っているんです。生まれつき病気なので、自分がどういうふうな立場で社会にいるかということが、研究をして、同じような人のことを知ったときに、初めて認識できたんです。今まで健常者っていう人たちについていくのが精一杯で、自分にとって何が良くて何がしたいっていう、その比較対象を、言葉として言えなかったんです。溶け込むっていうことが常にあったのです。そこに気づくまででも、すごく時間がかかりました。
伊藤 大学院のご研究はどんなテーマだったんですか?
ムーン ステロイドホルモンが出ない人がどんな生活をしているか、コロナ禍でオンラインでインタビュー調査をしました。いろんな今言ったような悩みを言っていいんだ、っていうことに気づきましたね。まずもって、まずその悩みが自分の問題じゃなかった、悩みを自分から切り離せた。ずっと性格の問題にされてきたので、それを切り離したっていうのが一番大きかったです。
伊藤 切り離せたっていうのは、言語化できたっていうことですか?
ムーン 人に話して、SOSを出すということです。なんかこう客観性が生まれてきた。今までは「あなたの都合で社会は変わらない」という感じだった。今も変わりはしないんですけれども、客観性が出てきた感じです。
伊藤 インタビューを通じて、ムーンさんがこれまで性格の問題だと考えさせられてきた部分を、全然違う語り方で語っていたっていうことですね。
ムーン そうなんです。 社会的には証明されてないんですけれども、共有された感じ、安心感がありました。人に言っていいんだ、と思えたのが大きかった。今までは、ちょっと気に入らないことを言っても、否定されていたのが、インタビューでは、肯定も否定もしませんけど、フラットで話せるというのは初めてでした。
伊藤 今まだ人に言えてないことってどのくらいある感じがしますか?たとえば最初に会った人には100言えてないことがあったとして、それが今全部外に出せてる感じなのか、まだ全部じゃない感じなのか。
ムーン 今は話せることは話しています。でも小学校から自分はやっぱり演じてきてるので、まわりが私についていいとか悪いとか言ってるのは、私じゃないんですよね。社交的で明るくできるぶん、思っていることは真逆っていう矛盾がありました。
伊藤 演技ができないぐらいのボロボロなムーンさんを誰かに見せたことはありますか?
ムーン そこはやっぱ癖ついちゃってるのかなと。そう思ったときには、コミュニティごと離脱するっていう感じで生きてきたかもしれない。
伊藤 そこで、全体重を誰かに預けられたら何か変わるかもしれないですね。
ムーン そこは自分も探しています。今初めて言われて、そういうふうなところをやっぱり自分の求めてるんだろうと思いました。
@2025/4/5 戸越銀座のカフェにて