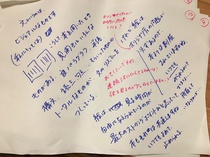黒坂祐さんは色覚障害のあるペインター。個展開催中の四谷未確認スタジオ(元銭湯)にてお話を伺いました。彼曰く、「色が司っているシステムがあまり効いていない」世界について。絵を描くときには、色が持つ力を色以外の方法(たとえば線の震え)で出しているそう。身体的条件の差異が要請する「翻訳」は常にコンセプチュアルかつ感覚的で、圧倒されます。
黒坂祐さんプロフィール
1991年千葉県生まれ、2019年東京藝術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻油画修了。近年の個展に、「荒れた庭、空っぽの部屋からの要請」(四谷未確認スタジオ、東京、2018)、「きょうまでいきてこられてよかった」 (野方の空白、東京、2017)、グループ展に、「絵画・運動(ラフ次元)」(四谷未確認スタジオ)など。「シェル美術賞2019」グランプリを受賞。現在は絵画制作を主軸に置く。
◎後天的な共感覚
伊藤 いまの見え方的にはどんな感じですか?
黒坂 色覚異常で一番多い型なんですけど、赤みが抜けるというのが、一番分かりやすい症状ですね。
伊藤 気づいたのはいつ頃ですか。
黒坂 小学校3年生くらいのときに健康診断の一環でテストがあって。そのときに保健カードみたいなのに書かれて、両親に見せたら、なんとなく感づいていたようで。
伊藤 なるほど。ご自身にとって当たり前なので説明しにくいと思うんですけど、赤が見えないというのはどういう感じですか。この部屋でこの椅子に一番近い色味のものはどれですか?
黒坂 そうですね…。壁の茶色か、もしくはあのビールの瓶(ハートランド)とかですかね。ビールの瓶は緑色だと知っちゃっているんですけど、色的には近いですね。緑と赤がかなり見分けが難しい色で。たとえばウィルキンソンのジンジャーエールのラベルは、茶色と緑がありますが、どっちがどっちかと言われると難しいですね。
伊藤 いまおっしゃった「ビールの瓶が緑色だと知っちゃってる」ってどういう感じなんでしょうか。感じられないけれど、頭の中で知識として持っておく、みたいなレベルがあるということですか?
黒坂 そうです。絵のタイトルも「後天的な共感覚」というものなんですけど、共感覚って先天的にこれがこう見えるというのとは別に、知識として、文化的要因で起こるということがあって、色弱はそれが強いという研究があります。感覚的に色が認識できないので、知識としてストックして、訓練して染み込ませておいている。逆にそれで間違えるというパターンもあるんですけど。ぼくがいつも話すのは、ペットボトルのホットのキャップはオレンジ色ですよね。でもお茶が多かったんで、それを黄緑だとずっと勘違いしていたんです。ビールの瓶も、実際にはオレンジだったとしても、ぼくは緑だと思っていたりします。そういったことで絵の色も決定していたりします。
伊藤 それが「後天的な共感覚」ということ?
黒坂 そうです。ぼくが色を決定したり、形に色を見たりするときの判断が、正常な人とズレがある、先入観の強度が違う。そこに意味の分解も含めて、今回はやっています。
伊藤 面白いですね。ある種、自分の感覚を否定するということなのかなと思うんです。もう一つの自分を作るというというか、分裂的なところがありますね。そこをどういうふうに処理しているのかが気になります。
黒坂 そうですね…自分の感覚みたいなものが、予備校とかで絵の訓練をしていくなかで、結構マジョリティの視覚に合うようにトレーニングしてきているところがあります。見て評価を下す側がそっちですから、ズレをなるべく抑えるようにしてきた。最初のぼくの色彩感覚みたいなものは、あまり自覚的でないかもしれないですね。「自分にはこれが綺麗に見える」というのと、「一般的にはこれが綺麗に見える」というののあいだで、常に揺れながら判断している感じですね
伊藤 これが綺麗だと言われているけど、自分的にはしっくり来ていなかったりするわけですね。
黒坂 そうですね。これは綺麗だと思うけど、一般的には綺麗なのはこっちだから、という調整が常にある感じですかね。
伊藤 でも知識と感覚の境目って微妙ですよね。たとえばこの机が100万円だと言われたら、なんかすごいものに見えてくるというか。知ると感じられる、というレベルがあるように思います。
黒坂 そうですね。だから見たことがない色に出会ったときは、わりと素直な感覚があるかなと思います。木の幹も、植物は緑だと思っていたんで、あれも緑の一種だと思っていたんです。キウイも微妙な色をしてますよね。茶色っぽい、赤っぽいんですけど、くだものの皮は緑だと思っていた。やっぱり「果物」とか「植物」とか、知識があるとそうなってしまいますね。「鉱物」「宝石」とかになってくると、どんな色になっていても不思議じゃないので、わりと自分の感覚で見られるんですよね。
伊藤 なるほど。たしかに植物はけっこうやっかいですね。なぜここがこの色なんだ、と言われると困るようなものがありますね。
黒坂 さらに木の幹に苔とかがついている場合も…
伊藤 わ、また緑でてきますね
黒坂 そう、でも面積的には少なくてもじっくり観察するわけではないから、緑だなってなんとなく思っていて。たとえば落書きをするときに色鉛筆がたくさんあったら緑をチョイスしてしまうかもしれない、というのがあります。
伊藤 知っているからこそ推理しすぎちゃうことがあるわけですね。
黒坂 そうですね。一般的にはあまり行われない工程ですよね。
伊藤 硬さとか柔らかさは見て分かるんですよね?さっき絵のことを話していたときに、色と形と質感、というふうにおっしゃっていて、その「質感」の部分が気になりました。
黒坂 硬さ、柔らかさはわかります。いままで、形でしか勝負できなかったんですよね。受験も経て、大学も経ていくなかで。なので形に関しては敏感なのかなと思います。質感も判断材料として、何かを見たときにより多くの情報を得ようとするので、けっこう気をつけて見るところかな、と。
◎ロスコの赤い絵を攻略する
伊藤 絵の話をもう少しうかがいたいのですが、絵の作り方と色彩が捉えられないことは、どんなふうに関係していますか。
黒坂 たとえば油絵をやるとなると、まず絵具を選ぶところから始めないといけないんです。そもそも色って名付けがない状態がふつうだと思うんですけど、絵具は製品化されて小分けにされてチューブに入っている。予算の限りもあるなかでそこからチョイスして買うときに、まずぼくは赤とか紫とかオレンジとかは、そもそも選ばないですね。かなりリスキーなので。それで結果的に、中間色とか、地味な色が集まってくる。それで、たとえばマーク・ロスコの赤い抽象画とかを、どうやって攻略していくか、ということを考えます。絵の強さ、画面の強さを更新していかなきゃいけないときに、どういう構造上の強さをもてばいいんだろう、ということを考えながら作っています。かなり絵の中の構造を組み立てる方です。色は、たとえば赤だったらパッション、血、炎みたいな感情を引き出してくれるということが起こる。でもそれがない状態で絵をつくるわけだから、感情を引き出さずに、どうやって身体に効果を与えていくかということを考えます。たとえば形をひとひとつ覆うことだったり、線の震えだったり、質の違いだとか、あとは今回の絵で言えばちょっとした円環構造になっているとか。そういった効果の積み重ねで、色による身体的な影響に匹敵するパワーを持たないといけないと思っています。それは最初に念頭に置いています。ぼくの絵は弱いほうなので。
伊藤 面白いですね。確かにさっき見せていただいた絵の線の震えって、染みてくる感じがあって、色彩的と言えるのかもしれないと思いました。いま説明を聞いてすごく納得感がありました。
黒坂 ミッフィーの作者のディック・ブルーナが、当時はああいうシンプルな面的な構成で絵本をつくるというのがかなり挑戦的だったようなのですが、その中で線の震えを開発したそうです。すごくゆっくり描くと線がふるえるので、それが結果的に画面の強度を出していた。そういう話には影響を受けています。あれがもとの絵の道具というか下絵というか道具なんですけど、いままで線でやっていたのを、ハサミでやろうとしています。ハサミってストロークが決まっているじゃないですか。あれで震えを出したり、小刻みなエッジを出すという実験をしてみました。キャンバスの網目と線のがたつきがリンクする方法は、線よりはハサミなんじゃないかなと思って。
伊藤 面白いですね。ものすごくコンセプチュアルだけど同時に身体的ですね。
黒坂 そうですね、結局感覚に訴えるためのコンセプトだったり、作りだと思います。
伊藤 そもそもなぜペインターになったんですか。
黒坂 ぼくはずっと絵が好きだったわけではなくて、もともとデザイナーになりたかったんです。デザイン科志望で予備校に入ったんですけど、実物よりも美しく描くということが全然できなくて、その道は挫折したんです。それで、油絵は固有色を無視して描けるということを知って、それで移ってきたんです。もともとはもっと大衆に向けたものづくりがしたかったんです。でもそれは自分自身がマイノリティだとやりづらいということをそのとき感じました。

◎不透明の歴史としての絵画
伊藤 赤って感情をかきたてるものであると同時に、「赤味」みたいなものがありますよね。人間の場合は血液が赤いからだと思いますが、皮膚の赤みのように、そこに生命を感じる、内側のみずみずしさを感じることと関わっているのかなと感じます。
黒坂 顔が赤らんでいることがぼくは分からないです。ピンとこないままいろいろな会話を聞いていました。あとはぼくは牛肉が苦手なんです。これは関係しているか分からないですけど、焼肉を食べるときに、赤から茶色に色が変化するということがあまり分からない。もともとがかなり茶色く見えていて、肉に対する、赤から刺激されるものがないんですよね。
伊藤 確かに豚や鳥は赤くないけど牛肉はすごく赤いですね。思ったよりいろいろなことの感じ方が変わりますね。
黒坂 昼の景色より夜の景色のほうを作品に使うことが多いですね。太陽光と人工灯では波長が全然違っていて、昼の光によってきれいに見えるものがそんなにきれいに見えていない。それよりも夜の光によって照らされているもののほうが、コントラストがついて美しく見えます。すごく強い光によって透ける色の美しさというのはいまいちピンとこない。夜の光は反射するものが浮き出てくる。車のライトを反射するガードレールとか。ああいうものがぼくは美しいものだと思っていて。フラッシュをたいたときの植物の緑なんかも好きですね。透けるものと反射するものというのは、現時点では勘ですけど、これから調べていきたいことです。確実に影響はしています。
伊藤 人工物のほうがいいという感じですかね。
黒坂 そうですね。ペンキの色とかはすごく惹かれるものがありますね。絵が好きっていうことじたいも、それに近い。絵はやっぱり不透明の歴史だと思います。ステンドグラスのようにもともとは透明だったものを、いかに不透明な中で、光をポータブルにするかという歴史だと思っています。
伊藤 光を不透明の問題として捉えてらっしゃるというのが面白いですね。
黒坂 予備校時代に、モネとかの印象派をずっと模写させられていたんですけど、彼らも固有色というものをできるだけ分解して、光の色で物を描いていますよね。あそこで描かれている色は共感するものがあって、光そのものを描くというよりは反射したものを描く。あれはすごく綺麗だなと思います。
伊藤 高緯度の地域に住むといいかもしれないですね(笑)ヨーロッパの光ってものすごく反射しますよね。
黒坂 一時期スイスに住んでいたんですけど、もうビカビカで(笑)。日差しが強いし、湖も真っ白で。日本の冬はけっこう空気が澄んでいる分、光が反射しますね。冬のほうが好きですね。
伊藤 光の反射と色覚の問題はどういうふうに連動しているんですかね。
黒坂 光の三原色のうち一番短い波長の赤が少し欠けるということなので、自然界がそれを前提にして成り立っているとすると、それがない世界というのは、本質的には生きることにあまり向かないんだと思います。霊長類が初めて赤を認識する色覚を手に入れたそうなのですが、それは果物の実を識別するためだったと。逆に植物は緑だから赤にすることで補色になるので食べられやすくなる。ぼくの場合はそれが逆転していて、実は目に入らなくて、緑のほうが入ってくる。色が司っているシステムがあまり効いていない。
伊藤 色が司っているシステムというのは面白いですね。もちろん人間の見え方だけがすべてではなくて、たとえば昆虫にとってはまったく別のシステムがあるんでしょうね。
(2020年1月28日四谷未確認スタジオにて)